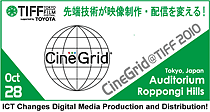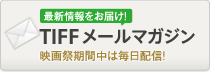2010.10.26
[インタビュー]
アジアの風 レハ・エルデム監督 インタビュー 第1回(10/26)


©2010 TIFF
――この度は、長編6作品の一挙上映ということで、あらためてデビュー作『月よ』(1988)から最新作の『コスモス』(2009)まで観ていくと、1作ごとの作風の変化に驚かされます。『月よ』は、白黒フィルムを用いた無国籍風のゴシック・ファンタジーでしたが、次の『ラン・フォー・マネー』(1999)、『ママ、こわいよ』(2004)では一転して古典回帰とも思えるコメディを展開し、その後『時間と風』(2006)、『マイ・オンリー・サンシャイン』(2008)では音と映像じたいが語りかけるような方向に深化を遂げてきました。こうした作風の変遷について、まず監督の考えをお聞かせください。
いまになって振り返ると、それぞれの作品が私の中で結びついているのを感じます。それぞれが繰り返されている。そう言ってもいいのかも知れません。映画というのは豊かなフォーマットであり、その中には多くの要素があります。各々の異なる要素を各々のかたちにするわけです。『ラン・フォー・マネー』ではストーリー展開に重きを置きましたが、『時間と風』では時間や空間といった別のアクセントで表現してあります。それぞれが別の条件を表している。同じやり方で映画を撮るのは私には退屈であり、あまりしたくありません。ひとつの庭で別々の作物を作る方が好ましいと思います。
――大局的に見て、映画作家には2つのやり方があると思います。小津安二郎のようにひとつのスタイルを洗練させていくタイプと、ジャン=リュック・ゴダールのように作品ごとにスタイルを変貌させていくタイプです。
小津もゴダールも自分には大変素晴らしい先達であり、大好きな映画作家です。ゴダールは先ほどお話しした意味で、私の考えに近いと思います。映画という大きなフォーマットがあって、その中にいろんなものがある。それぞれの要素を使い、それぞれの作品を奏でるわけです。一方ではアッパス・キアロスタミのような人もいて、彼もまた素晴らしい映画を作っていますが、同じような作品を作り、同じような撮り方をしている。それはそれで素晴らしいのですが、私には退屈に感じてしまう時もある。これはもちろん、キアロスタミを侮辱するために言うのではありません。けれども、ゴダールは作るごとに作品世界が新しくなっていきます。小津安二郎もキアロスタミと同じように、私にとっては手本となる先達です。それぞれの作品にテイストがあって素晴らしい。でも私には、ゴダールのように作品ごとに新しくなるほうが好ましい。たとえ、それが微差に過ぎなくても。
――でも作風が変化する中で、監督が作ったキャラクターにはいくつかの共通点が見受けられます。両親もしくは片親のいない子供、親が病気がちで介抱している子供、誰にも受け容れてもらえない孤独を動物虐待で表現するしかない子供。これらはみな同じキャラクターのようです。このような人物が一連の続き物のように登場することには、はたしてどんな意味があるのでしょう?
あとから遠望して見れば、そうしたことが言えるのでしょうが、これは私自身のちになって知ったことなのです。映画の制作中はそうしたことは考えていません。表面的な部分はおくにしても、内的な部分では私自身の問題が投影されている。だから気にもかけずにやり、後になって結果的にそうだったと知るわけです。たとえば『月よ』の少女が、自分の過去を演じていると知ったのはつい最近のことです。それがわかった時には心底驚愕しました。こうした役柄について、私はキャラクターではなくてフィギュアと捉えているのですが、一連の場面が実際に私が体験した出来事と精神レベルで非常に似通っており、少女は自分であると発見するに至ったのです。
――親に隠れてタバコを吸うとか、割礼をこわがるとか、そうした子供の頃のエピソードは監督自身の体験に基づいているとのことですが、実はこうした個々の出来事以上に、監督は人物の心理的側面に重点を置いているわけですね?
その通りです。
――人物=フィギュアを造型するにあたり、監督が特別に注意していることはありますか?
現実ではないレベルで、フィギュアを動かすことです。『ママ、こわいよ』には何人ものフィギュアが登場しますが、それぞれが実際にある人間とは違う作られたものです。生身の人間の姿とは切り離して、まったく別のレベルで提示しているのです。これは肝心なことです。現実に基づくもの、日常生活から切り取られて、そのまま隠しカメラで覗いたようなもの、そうしたナチュラリズムに基づくものは私の好みではありません。それぞれのフィギュアが創作されたものであり、それぞれがひとつの夢の中にあるというのが私の理想です。映画にはイスタンブールの人々がよく出てきますが、実際のイスタンブール人とはまるで違います。『ママ、こわいよ』の母親にしても、実際にいるような母親ではなく、そうして作られたフィギュアなのです。強くて男性さえも圧倒しそうな迫力ですが、その中に様々なものを内包する力があって情愛に満ち、声もたくましい。このように実際には私が知らない人間―こんな人物が私の母親だったら途方に暮れてしまうと感じるフィギュアを作りだすことが、映画の役割なのです。母親とは正反対に、息子のケテンは始終縮こまり、声のトーンもまったく異なるフィギュアです。このように一連のフィギュアをオモチャのように作っていくのです。
――フィギュアの形態的側面についてもお尋ねしたいと思います。『月よ』の少女が物語の前半で、部屋の中で仰向けに寝ているポーズは、画家のバルテュスが描く構図にそっくりです。こうした絵画や映画の素養は、自身の作品にどれだけ意図的に反映させているのですか?
それは意図的にやることもあれば、自然に出てくるばあいもあります。フランスにいた時は映画とともに造形美術を学んでいました。どちらも好きなのです。好きな画家はさまざまいてバルテュスもそのひとりです。『月よ』ではその後、トランプ占いをしている少女のもとに叔母がやって来て、「おやおや(Patience !)」と言うのですが、この場面などもそうです(注 バルテュスに同じような構図の絵があり、題を「La Patience(トランプ占い)」という)。当時はバルテュスとエル・グレコの間に関連はないかと考えたりして、そうした符号を意図的に取り入れました。こうしたことをするのが私の好みです。このことは絵に限らず文学作品についてもそうで、トルコ文学の作品から登場人物の名前を拝借したりもします。最近では『コスモス』の中に3人兄弟が出てくるコミカルな場面がありますが、あれは『カラマーゾフの兄弟』を意識しました。
――前半の親殺しと遺産の話をする場面ですか?
そうです。映画の世界というのは、そうした広いフォーマットがあって、すべてその中に配置するわけです。たとえば、好きな食べ物や嫌いな食べ物を集めて配置したり除外したりする。バルテュスの例もそうです。撮影監督のフローラン・エリーとは『ラン・フォー・マネー』以来ずっと一緒にやっていますが、脚本を作る前にどの絵画を次回作の背景にするのか話し合います。その映画の精神や色彩をまず決めるわけです。『ラン・フォー・マネー』の時には、エドワード・ホッパーを意識しました。こうして最初に設定しますが、作業するうちに別のものに替えようとなることもあります。今回フローランも来ていたら、東京で一緒に美術館を見て回って、映画のアイデアでも検討しようと思っていたのに残念です(笑)。
(聞き手:赤塚成人)
第2回インタビューに続く