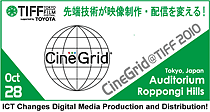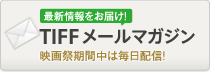2011.02.23
[更新/お知らせ]
第5回映画批評家プロジェクト 結果発表
第5回映画批評家プロジェクトの受賞作品が決定いたしました。
今回も大勢の皆様からの応募をいただき、大変ありがとうございました。
審査の結果、佳作3名を選出いたしました。
今後の皆様のご活躍を願うと共に、応募して下さいました皆様に心より感謝いたします。
本年で5年目という節目を迎えた『映画批評家プロジェクト』は今回で終了させていただくことになりました。皆様からの多数のご応募、誠にありがとうございました。
今後より一層企画の充実を図り、また新しい形で映画人の育成に貢献できればと思っております。
審査委員: 品田雄吉、土屋好生、明智惠子(キネマ旬報編集長)
表彰式の模様はコチラから
佳作:
鎌田亜子 Ako Kamata 『ビューティフル・ボーイ』
斉藤賢弘 Yoshihiro Saito 『ゼフィール』
古川 徹 Toru Furukawa 『隠れた瞳』
※クリックすると、各受賞作をお読みいただけます。これから作品をご覧になる方は、内容に触れている箇所がありますのでご注意ください。
※受賞者アイウエオ順
◆佳作
『ビューティフル・ボーイ』 鎌田亜子
「少年と少女は海に出た」。子供の声のモノローグで始まるこの世界は、その子供にとっては終わりを意味するのだが、少年と少女にとっては、とてつもなく長い航海の幕開けだったのだ。
映画には題材というものが必要で、この作品についてはきっと校内銃乱射事件とでも説明づけるのであろう。しかし、この映画には今まで描かれてきたような人々の好奇心を刺激するようなバイオレンスもないし、青年たちのはち切れんばかりの反逆精神を駆り立てるような要素はない。これは、私たちが今まで観てきたものとは違う。事件を起こした息子・サムの母親役のマリア・ベロの恐ろしいほどの凍てついた表情が、そう思わせるまでに時間はかからなかった。
事件が起こると、当然のごとく周囲からの詰問が始まる。行き場をなくしそうになった父親のビルと、母親のケイト。しかしその居場所は、思い出を振り払うかのように売買しようとしていた、元々空っぽの場所だった。まるで家をなくしかのような少年と少女は、波にのまれるようにして、一歩外の世界へと踏み出す。母親の弟夫婦の姿は、まるで模範教育を見せつけるかのようで、二人は初めて不自然でない子育てを目の当たりにする。マスコミや周囲の視線よりも辛いものは自責の念であり、両親は、漫然とする時と記憶の中で、自分たちを繋ぎとめようとすがりついていた一つのものに気付く。息子と共に家族全員で旅行をプランしていた母親は、父親のよそよそしい態度に愛想を半ば尽かし、彼もまた、スペルチェッカーである母親を、職業癖のせいか息子を正してばかりだと叱責する。息子が銃を乱射するに至った動機は、この映画の中では実ははっきりとは示されない。途中、「お前たちがこうさせたんだ」とサムが形相を変えた恐ろしい映像もニュース上に流れるのだが、それは「お前たち」に対しての彼であり、両親に対しての息子ではない。彼は事件を起こす前に両親に対して謝罪の映像も撮っている。それは彼らだけに晒される本当の顔であり、それは二人の中に根付いてた息子への愛情を逆なでさせる。父親と母親は、逃避行先のモーテルでまるで初々しい恋人同士のように時を過ごす。息子を失ってのこの男女は、もはや母親と父親ではなく、行き先も分からぬような少女と少年に還る。
必死に悲しみと後悔の念を紛らす父親の像が良い。冒頭の、妻を交わしての息子との三人の電話は実に素っ気ない。そう、子供なのは息子だけではなかったのだ。二人は息子を授かった日から、彼と同じ時間だけ親として生きてきた、つまり両親も息子と同じ年だとも言えるのだ。
世界はずっと神経質で、感情も予測不可能に溢れてしまうが、ここではそんな人間の姿が脚色されることなく描かれている。事件の裏側は、ワイドショーで編集されるようなドラマチックなものではない。そこには大海原で溺れそうなのをこらえて手を取り合う少年と少女がいるだけだ。
良くとも悪くとも、ものごとは変わりゆく。そう悟っていた息子は、両親にとってのオール(櫂)となり、彼らは悲しみを波にして、欲も悪くも分からない世界に何度も生まれ、善悪すらも無意味な世界に飲まれていく。人間が美しい姿というのは、必ずしも光り輝いているときではないのだ。少年、少女の心に返って、悲しみに泣くことができたあの父親もまた、一人のビューティフル・ボーイなのだろう。
◆佳作
『ゼフィール』 斉藤賢弘
人生に辛いことは数あれど、「待つこと」はその中でも五指に入るものであると私は確信している。自分では何も出来ない、その無力さが疎ましく憎らしいのは勿論のこと、自分がこれだけ願い望んでいるのに、肝心のその対象は少しも近付いてきてはくれない。思い通りにならないことがもどかしく、待ち続ける果てにちっとも先が見えてこない事が痛く、辛くて仕方が無い。誰もが一度はそのような経験をしたことがあるだろう。
『ゼフィール』は一言でいうなら、「待ち続ける」作品だ。
大都市イスタンブルでイメージする、オリエンタルな雰囲気が色濃いトルコの姿とは程遠い、寂しげな片田舎の村落で主人公ゼフィールは来る日も来る日も母の到来を夢想し、待ち焦がれる。極度に音や台詞が殺ぎ落とされた画面からは、ただ彼女の苦しさや苛立ちだけがひりひりとして伝わってくる。
「待つこと」が時として恐ろしいのは、本人にとって長い間待ち続けるうちに「自分が一体何を待っていたのかが分からなくなっていくこと」に他ならない。ゼフィールにとっても自分が熱望しているのが「自分を喜ばせる母の姿」なのか、「自分を苦しめ続ける母の死の姿」なのかがほんの一瞬だけ、一瞬ではあるが混合されていく。
思えば、監督ベルマ・バシュの作品は一貫して「何かを待つこと」がその通低音を成している。処女短編『Poyraz』も河辺にて何か「得体の知れないもの」をじっと待ち続ける少女の物語だった。何かが起こりそうな不安定な気配、影や闇を効果的に用いての場面設定。それは私達をどこか落ち着かなくさせるのに十分だった。
『ゼフィール』は『Poyraz』を多くの点で継承している。が、異なる部分もやはり在る。『Poyraz』ではぼんやりと明示されない「危うさ」「不気味さ」は、数年後の長編作品『ゼフィール』では、はっきりとした形を持って私達の前に姿を現す。
時に、登場人物達よりもクローズアップされる生き生きとうごめくかたつむりやとかげ等の生物達、対し既に生命を失い、もう動くことなく埋葬されるだけの亡骸。
何度も映像を見せられるうち、私達の中で生・死の境は徐々に低くなり、やがて違和感を持たないまでになっていく。それは、帰還したばかりの母親とゼフィールとの不穏な緊張関係と相まって、やがて訪れる破局を観客達に受け入れさせ、理解させることに、これ以上無いほどの効果を挙げている。この映画からは漲る生命力以上に、どこか死の気配を覚える。
さてゼフィールにとってこれほどまでに待ち焦がれた「母親」はどのような存在であったか。
母親は彼女にとり唯一「愛情を注がれる」だけでなく「愛情を注ぐことが出来る」存在だった。それが出来ない時、彼女が必死で憎むことが出来る存在だった。いびつなまでに感情をぶつけられる存在だった。
観客である私達は、それとどこか似た存在をもう知っている。そう、それは自分だ。思う時に愛情を注ぎ、思う時に憎しみをぶつける。自分を慰めるが、同時に自分を深く傷つける。思い通りに出来そうで、決して十分に制御出来ない唯一の存在、それが自分自身だ。
ゼフィールが母親を最後崖から突き落とし、他の生物の亡骸と同じように葬ることで、彼女は同時にそれまでの自分を殺し、埋葬したのだ。「ただ待つだけの幼く純粋だった」自分と決別したのだ、永遠に。でも、それはなんて悲しいことだろう。
『ゼフィール』には心の底に貯まっていつまでも流れていかない静かな痛みと悲しみがある。それはとりもなおさず、私達が大人に成長する時にどこかでつけられたものと似ている。だから、私はこの映画をどこか忘れられずにいるのだろう。
◆佳作
『隠れた瞳』 古川 徹
初めて観たアルゼンチン映画『オフィシャル・ストーリー』の衝撃は20年以上過ぎた今も鮮明に記憶している。その後も『スール/その先は…愛』『ブエノスアイレスの夜』、そして『瞳の奥の秘密』など硬質なアルゼンチン映画が、軍事独裁政権の暗い時代と向き合い、その罪を告発してきた。『隠れた瞳』もまたその系譜に位置するが、決して既成のイメージに収まり切る作品ではない。思想弾圧を直接的に描かず、学校という空間に権威主義とマチスモ(男性優位主義)による支配構造を再現することで、背景にある体制の脅威を想起させる大胆なプロットと、映画的技法の多彩さは特筆に値する。
1982年、軍事政権末期のブエノスアイレス。エリートを養成する国立高等学校を舞台に、タイトルが暗示する監視という行為を通して時代の闇を描く。高い壁に囲まれた閉鎖的な校舎で、教員が生徒に監視の目を光らせ、厳格な管理教育が行われている。23歳の女性教員・マリアは風紀の乱れを正すという口実で生徒の監視を始めるが、やがてその目的は性的快楽に転じる。彼女はマチスモによる女性への抑圧の反動を、教育者のモラルの喪失という矛盾によってリアルに体現する人物である。一方、マリアの上司・ビアスートは軍事政権の力の象徴であり、口ひげを蓄えた威圧的な風貌で生徒を服従させて支配欲を満たす。政権と信条を共有する人物である。
この二人を軸に、息詰まる心理劇が多彩なショットを駆使した緩急に富んだ筆致で綴られ、カメラが“隠れた瞳”となって監視国家の狂気を映し出す。チェス盤のような規則正しい格子柄が施された中庭を俯瞰するショットによって、生徒たちが盤上の駒のような従順さを強いられる教育環境を深く印象付ける。校舎の階段を駆け降りるマリアを頭上から捉えたショットは実に威圧的で、彼女もまた階層化された力の序列に組み込まれ逃れられない諦観が滲む。光と影のコントラストを強調した照明が作り出す人物の陰影は、あたかもその内面の闇を見透かしているかのようだ。
台詞より瞳で多くを語る役者たちの表現力も見逃せない。その視線が欲望や憎悪などの感情の強度と方向を示すベクトルとして機能する。男子生徒へのマリアの秘めた欲望にビアスートが気付く集会の場面は、複雑に交差する感情のもつれを三者の視線によって見事に表現している。
そして、クライマックスの急転直下の展開に思わず息を呑む。トイレを舞台に、ビアスートがマリアの負い目に乗じて醜い欲望を満たし、彼女の憎悪に火を点ける。カメラは事件の顛末を一定の距離をおいて捉え“隠れた瞳”に徹することで高い緊張感を生み出している。鏡を巧みに利用して怒りの一撃をマスキングする緻密さと、高慢な抑圧者の末路を観客に“監視”させて軍事政権の終焉を予感させる大胆さ、技術とプロットの融合による映像のインパクトに圧倒される。全編を通してカメラの機能が駆使されているが、決してテクニックを誇示することが目的ではなく、硬質なテーマがあり、それを観客の意識のより深層へと伝える手段として卓越した技法が用いられている。
軍事クーデターが起きた1976年生まれの新鋭ディエゴ・レルマン監督は、直情的に軍事政権を糾弾せずに、そのアンチテーゼを豊かな映像表現に昇華させた。世代間の温度差は感じられるが、約30年前の思想弾圧の遺恨が今尚アルゼンチン映画のモチベーションになっていることからも、癒えない傷の深さを窺い知ることができる。
今回も大勢の皆様からの応募をいただき、大変ありがとうございました。
審査の結果、佳作3名を選出いたしました。
今後の皆様のご活躍を願うと共に、応募して下さいました皆様に心より感謝いたします。
本年で5年目という節目を迎えた『映画批評家プロジェクト』は今回で終了させていただくことになりました。皆様からの多数のご応募、誠にありがとうございました。
今後より一層企画の充実を図り、また新しい形で映画人の育成に貢献できればと思っております。
東京国際映画祭事務局 映画批評家プロジェクト一同
<第23回東京国際映画祭 映画批評家プロジェクト>
審査委員: 品田雄吉、土屋好生、明智惠子(キネマ旬報編集長)
表彰式の模様はコチラから
<第5回映画批評家プロジェクト 結果発表>
佳作:
鎌田亜子 Ako Kamata 『ビューティフル・ボーイ』
斉藤賢弘 Yoshihiro Saito 『ゼフィール』
古川 徹 Toru Furukawa 『隠れた瞳』
※クリックすると、各受賞作をお読みいただけます。これから作品をご覧になる方は、内容に触れている箇所がありますのでご注意ください。
※受賞者アイウエオ順
◆佳作
『ビューティフル・ボーイ』 鎌田亜子
「少年と少女は海に出た」。子供の声のモノローグで始まるこの世界は、その子供にとっては終わりを意味するのだが、少年と少女にとっては、とてつもなく長い航海の幕開けだったのだ。
映画には題材というものが必要で、この作品についてはきっと校内銃乱射事件とでも説明づけるのであろう。しかし、この映画には今まで描かれてきたような人々の好奇心を刺激するようなバイオレンスもないし、青年たちのはち切れんばかりの反逆精神を駆り立てるような要素はない。これは、私たちが今まで観てきたものとは違う。事件を起こした息子・サムの母親役のマリア・ベロの恐ろしいほどの凍てついた表情が、そう思わせるまでに時間はかからなかった。
事件が起こると、当然のごとく周囲からの詰問が始まる。行き場をなくしそうになった父親のビルと、母親のケイト。しかしその居場所は、思い出を振り払うかのように売買しようとしていた、元々空っぽの場所だった。まるで家をなくしかのような少年と少女は、波にのまれるようにして、一歩外の世界へと踏み出す。母親の弟夫婦の姿は、まるで模範教育を見せつけるかのようで、二人は初めて不自然でない子育てを目の当たりにする。マスコミや周囲の視線よりも辛いものは自責の念であり、両親は、漫然とする時と記憶の中で、自分たちを繋ぎとめようとすがりついていた一つのものに気付く。息子と共に家族全員で旅行をプランしていた母親は、父親のよそよそしい態度に愛想を半ば尽かし、彼もまた、スペルチェッカーである母親を、職業癖のせいか息子を正してばかりだと叱責する。息子が銃を乱射するに至った動機は、この映画の中では実ははっきりとは示されない。途中、「お前たちがこうさせたんだ」とサムが形相を変えた恐ろしい映像もニュース上に流れるのだが、それは「お前たち」に対しての彼であり、両親に対しての息子ではない。彼は事件を起こす前に両親に対して謝罪の映像も撮っている。それは彼らだけに晒される本当の顔であり、それは二人の中に根付いてた息子への愛情を逆なでさせる。父親と母親は、逃避行先のモーテルでまるで初々しい恋人同士のように時を過ごす。息子を失ってのこの男女は、もはや母親と父親ではなく、行き先も分からぬような少女と少年に還る。
必死に悲しみと後悔の念を紛らす父親の像が良い。冒頭の、妻を交わしての息子との三人の電話は実に素っ気ない。そう、子供なのは息子だけではなかったのだ。二人は息子を授かった日から、彼と同じ時間だけ親として生きてきた、つまり両親も息子と同じ年だとも言えるのだ。
世界はずっと神経質で、感情も予測不可能に溢れてしまうが、ここではそんな人間の姿が脚色されることなく描かれている。事件の裏側は、ワイドショーで編集されるようなドラマチックなものではない。そこには大海原で溺れそうなのをこらえて手を取り合う少年と少女がいるだけだ。
良くとも悪くとも、ものごとは変わりゆく。そう悟っていた息子は、両親にとってのオール(櫂)となり、彼らは悲しみを波にして、欲も悪くも分からない世界に何度も生まれ、善悪すらも無意味な世界に飲まれていく。人間が美しい姿というのは、必ずしも光り輝いているときではないのだ。少年、少女の心に返って、悲しみに泣くことができたあの父親もまた、一人のビューティフル・ボーイなのだろう。
◆佳作
『ゼフィール』 斉藤賢弘
人生に辛いことは数あれど、「待つこと」はその中でも五指に入るものであると私は確信している。自分では何も出来ない、その無力さが疎ましく憎らしいのは勿論のこと、自分がこれだけ願い望んでいるのに、肝心のその対象は少しも近付いてきてはくれない。思い通りにならないことがもどかしく、待ち続ける果てにちっとも先が見えてこない事が痛く、辛くて仕方が無い。誰もが一度はそのような経験をしたことがあるだろう。
『ゼフィール』は一言でいうなら、「待ち続ける」作品だ。
大都市イスタンブルでイメージする、オリエンタルな雰囲気が色濃いトルコの姿とは程遠い、寂しげな片田舎の村落で主人公ゼフィールは来る日も来る日も母の到来を夢想し、待ち焦がれる。極度に音や台詞が殺ぎ落とされた画面からは、ただ彼女の苦しさや苛立ちだけがひりひりとして伝わってくる。
「待つこと」が時として恐ろしいのは、本人にとって長い間待ち続けるうちに「自分が一体何を待っていたのかが分からなくなっていくこと」に他ならない。ゼフィールにとっても自分が熱望しているのが「自分を喜ばせる母の姿」なのか、「自分を苦しめ続ける母の死の姿」なのかがほんの一瞬だけ、一瞬ではあるが混合されていく。
思えば、監督ベルマ・バシュの作品は一貫して「何かを待つこと」がその通低音を成している。処女短編『Poyraz』も河辺にて何か「得体の知れないもの」をじっと待ち続ける少女の物語だった。何かが起こりそうな不安定な気配、影や闇を効果的に用いての場面設定。それは私達をどこか落ち着かなくさせるのに十分だった。
『ゼフィール』は『Poyraz』を多くの点で継承している。が、異なる部分もやはり在る。『Poyraz』ではぼんやりと明示されない「危うさ」「不気味さ」は、数年後の長編作品『ゼフィール』では、はっきりとした形を持って私達の前に姿を現す。
時に、登場人物達よりもクローズアップされる生き生きとうごめくかたつむりやとかげ等の生物達、対し既に生命を失い、もう動くことなく埋葬されるだけの亡骸。
何度も映像を見せられるうち、私達の中で生・死の境は徐々に低くなり、やがて違和感を持たないまでになっていく。それは、帰還したばかりの母親とゼフィールとの不穏な緊張関係と相まって、やがて訪れる破局を観客達に受け入れさせ、理解させることに、これ以上無いほどの効果を挙げている。この映画からは漲る生命力以上に、どこか死の気配を覚える。
さてゼフィールにとってこれほどまでに待ち焦がれた「母親」はどのような存在であったか。
母親は彼女にとり唯一「愛情を注がれる」だけでなく「愛情を注ぐことが出来る」存在だった。それが出来ない時、彼女が必死で憎むことが出来る存在だった。いびつなまでに感情をぶつけられる存在だった。
観客である私達は、それとどこか似た存在をもう知っている。そう、それは自分だ。思う時に愛情を注ぎ、思う時に憎しみをぶつける。自分を慰めるが、同時に自分を深く傷つける。思い通りに出来そうで、決して十分に制御出来ない唯一の存在、それが自分自身だ。
ゼフィールが母親を最後崖から突き落とし、他の生物の亡骸と同じように葬ることで、彼女は同時にそれまでの自分を殺し、埋葬したのだ。「ただ待つだけの幼く純粋だった」自分と決別したのだ、永遠に。でも、それはなんて悲しいことだろう。
『ゼフィール』には心の底に貯まっていつまでも流れていかない静かな痛みと悲しみがある。それはとりもなおさず、私達が大人に成長する時にどこかでつけられたものと似ている。だから、私はこの映画をどこか忘れられずにいるのだろう。
◆佳作
『隠れた瞳』 古川 徹
初めて観たアルゼンチン映画『オフィシャル・ストーリー』の衝撃は20年以上過ぎた今も鮮明に記憶している。その後も『スール/その先は…愛』『ブエノスアイレスの夜』、そして『瞳の奥の秘密』など硬質なアルゼンチン映画が、軍事独裁政権の暗い時代と向き合い、その罪を告発してきた。『隠れた瞳』もまたその系譜に位置するが、決して既成のイメージに収まり切る作品ではない。思想弾圧を直接的に描かず、学校という空間に権威主義とマチスモ(男性優位主義)による支配構造を再現することで、背景にある体制の脅威を想起させる大胆なプロットと、映画的技法の多彩さは特筆に値する。
1982年、軍事政権末期のブエノスアイレス。エリートを養成する国立高等学校を舞台に、タイトルが暗示する監視という行為を通して時代の闇を描く。高い壁に囲まれた閉鎖的な校舎で、教員が生徒に監視の目を光らせ、厳格な管理教育が行われている。23歳の女性教員・マリアは風紀の乱れを正すという口実で生徒の監視を始めるが、やがてその目的は性的快楽に転じる。彼女はマチスモによる女性への抑圧の反動を、教育者のモラルの喪失という矛盾によってリアルに体現する人物である。一方、マリアの上司・ビアスートは軍事政権の力の象徴であり、口ひげを蓄えた威圧的な風貌で生徒を服従させて支配欲を満たす。政権と信条を共有する人物である。
この二人を軸に、息詰まる心理劇が多彩なショットを駆使した緩急に富んだ筆致で綴られ、カメラが“隠れた瞳”となって監視国家の狂気を映し出す。チェス盤のような規則正しい格子柄が施された中庭を俯瞰するショットによって、生徒たちが盤上の駒のような従順さを強いられる教育環境を深く印象付ける。校舎の階段を駆け降りるマリアを頭上から捉えたショットは実に威圧的で、彼女もまた階層化された力の序列に組み込まれ逃れられない諦観が滲む。光と影のコントラストを強調した照明が作り出す人物の陰影は、あたかもその内面の闇を見透かしているかのようだ。
台詞より瞳で多くを語る役者たちの表現力も見逃せない。その視線が欲望や憎悪などの感情の強度と方向を示すベクトルとして機能する。男子生徒へのマリアの秘めた欲望にビアスートが気付く集会の場面は、複雑に交差する感情のもつれを三者の視線によって見事に表現している。
そして、クライマックスの急転直下の展開に思わず息を呑む。トイレを舞台に、ビアスートがマリアの負い目に乗じて醜い欲望を満たし、彼女の憎悪に火を点ける。カメラは事件の顛末を一定の距離をおいて捉え“隠れた瞳”に徹することで高い緊張感を生み出している。鏡を巧みに利用して怒りの一撃をマスキングする緻密さと、高慢な抑圧者の末路を観客に“監視”させて軍事政権の終焉を予感させる大胆さ、技術とプロットの融合による映像のインパクトに圧倒される。全編を通してカメラの機能が駆使されているが、決してテクニックを誇示することが目的ではなく、硬質なテーマがあり、それを観客の意識のより深層へと伝える手段として卓越した技法が用いられている。
軍事クーデターが起きた1976年生まれの新鋭ディエゴ・レルマン監督は、直情的に軍事政権を糾弾せずに、そのアンチテーゼを豊かな映像表現に昇華させた。世代間の温度差は感じられるが、約30年前の思想弾圧の遺恨が今尚アルゼンチン映画のモチベーションになっていることからも、癒えない傷の深さを窺い知ることができる。