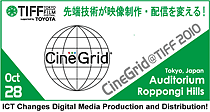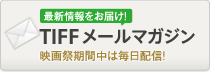2010.10.26
[インタビュー]
アジアの風『燃え上がる木の記憶』 シャーマン・オン監督 インタビュー(10/26)


©2010 TIFF
――もともと写真家としてスタートされたわけですが、映画作りには初めから興味があったのですか。
写真は十代の頃に始めました。カメラをプレゼントしてもらったので、まずペットを撮り、それから徐々に人物を撮るようになりました。大学に入るとビデオカメラを手に入れ、動画を撮るようになりました。動いているいないにかかわらず、映像に興味があったのです。私は映画学校出身ではないので、映画館で映画を見ることで映画作りを学びました。大学時代にボランティアで映画祭のチケットを売るのを手伝いながら、世界の様々な映画を見ました。そこから私の映画教育が始まったのです。最初のうちは夢中でいろんな映画を見ていましたが、ある時からそれらを忘れて、自分なりのスタイルを見つけようとしました。でも私の作品にそうした映画的な血統を見てとることはできるかもしれません。長編処女作の『はし』は福岡のアジア美術館で滞在研修をしている時に作りました。アーティストとして写真と映画を研究するためにそこにいたのです。私独自の製作方法を発展させたのは日本においてです。予算がない中でいかに映画作りをするかということを考え、自主的に協力してくれる非職業俳優と一緒に映画作りを始めました。制約の中で映画作りをするということはとても面白いことです。
――『はし』と同様、『燃え上がる木の記憶』は母国から遠く離れた場所で撮られましたが、監督のバックグラウンドに母国マレーシアの多民族性があることで、異国でもそれほど違和感を覚えることなく撮影できたのでしょうか。
『燃え上がる火の記憶』の舞台となるタンザニアの首都ダルエスサラームの気質は東南アジアによく似ています。撮影中、プロデューサーと「まるでインドネシアにいるようだね」と話していました。とても居心地がよかったです。私は福岡でも撮影しましたけれど、日本とインドネシアとの差の方が、アフリカとインドネシアとの差より大きかったです。例えばアフリカでは人と待ち合わせをしても45分から1時間くらい遅れるのが普通です。ですから、例えば15時に会いたい時には、14時15分に待ち合わせなくてはならないのです。ジャカルタもマレーシアもそんな感じです。

©2010 TIFF
――時間の流れ方が違うということでしょうか。
そうですね。時間が伸縮するものなのです。マレーシアでは「ゴムの時間」と呼んでいます。彼らの話し方はとてもアジア人に似ています。ダルエスサラームはかつてアフリカの奴隷貿易の港でした。アラブ人が奴隷貿易を始め、西洋人がそれを引き継ぎました。
――監督の作品は大半の部分がワンシーン=ワンショットで撮られていますが、そこに流れている時間の感覚も不思議な感じがします。
実は、今回の作品の方が前作よりもショットの持続時間は短くなっていて、前作に比べればMTVのビデオクリップみたいなものです。私はタルコフスキーにとても影響を受けました。彼の作品は長い移動撮影が特徴的ですが、私は台湾ニューウェイヴ式にやらなければなりませんでした。つまり三脚にキャメラを据えて、俳優たちに演技させるという方法です。小津もそうですよね。私は50ミリの標準レンズを使って普通のアングルから撮影しています。その方がスクリーン上で起きていることに観客の注意を向けることができるからです。そのことに写真を撮っていた時に気づきました。報道写真ではワイドレンズを使って遠近を強調したりしますね。しかし標準レンズだと観客は目をあちこちに動かして細部を見ることができます。
――50ミリレンズを使われているということでしたが、フィルムで撮る50ミリとデジタルで撮る50ミリだと画面の奥行きが変わってきませんか。
このキャメラ(CanonのEOS 5D Mark II )はフルフレームなので35ミリフィルムで撮るのとそれほど遠近感は変わらないです。このレンズを使えばフィルムで撮るのとほとんど同じように撮れます。普段、私の撮る画面は奥行きが深いのですが、大体のものがきちんと写ります。

©2010 TIFF
――画面の中の手前と奥の人物とのやりとりが面白いですね。
それが狙いです。自分で撮影もしていましたから、最初に撮りたい範囲がきちんと収まるような位置にキャメラを据え、後は演出に集中しました。
――適切な位置にキャメラが置かれているという印象を受けます。
おそらく伝統的な絵画のタブローについての考え方に由来していると思います。
――1910年代のサイレント映画に見られるタブロー的な演出法を思い起こさせます。
初期の撮影法に私はとても興味があります。そこでは空間と人物の両方を見ることができます。
――基本的にこれまでの三作品は非職業俳優を使われていますね。
ただ今回の作品では一人だけ役者を使っています。彼は大学の俳優科の学生です。基礎的な訓練を受けたことがあるのは彼だけでした。他の人たちはこれまで自分の人生を生きるという訓練を積んでいたために、生き生きと自分自身を演じることができたと思います。例えば十五歳の少女が出演していますが、彼女は人生において十五年間の訓練を積んでいたわけです。身体の所作が物語をきちんと語っています。それは学校では学ぶことができません。
――では非職業俳優たちに対して演技のレッスンをすることはされなかったわけですね。
一、二回リハーサルをしただけです。ただ最初にインタビューの時間を取りました。彼らの家族のことなどを尋ねたりして、そこから得た情報から脚本を作り上げました。彼らの実人生での出来事を多少変えて、よりドラマティックな構成にしました。例えば母親の墓を探している人物が登場しますが、実際に彼は母親をマラリヤで亡くしています。私はリハーサルの時に彼に亡くなった母親に宛てて手紙を書くように頼みました。プライベートな手紙なので最終的には映画では使いませんでしたが。掃除人が何か手紙を読んでいるシーンがありますけれど、それがその手紙です。プライベートなものはプライベートなままに留めておきたかったのです。
――そのあたりの節度が素晴らしいと思います。手紙をそのまま使っていたら、もっと品のないものになっていたかもしれません。
私は彼の手紙を読みましたが、とても感動的な内容でした。しかしそれを使っていたら、確かに語り過ぎになっていたでしょう。私たちは誰でも大切な人を亡くした経験がありますから、亡くなった人に向けて手紙を書く時の気持ちがどのようなものかはわざわざ見せなくても想像することができるはずです。小津安二郎の映画もそうですよね。日本映画の良いところは、見せなくてもわかることはあえて見せない点です。アジア人の大半に共通する感性だと思いますが。
――撮影クルーは何人くらいですか。
私の他に四人です。通訳を兼ねた助監督、録音係とその助手、それからスクリプターです。
――これまで一貫して少人数のクルーで撮影しているのですか。
できるだけコンパクトにしようと努めています。福岡で最初の映画を撮影した時には私と通訳、それに美術館のキュレーターだけでした。キュレーターは撮影されたものを見て時々台詞回しがおかしくないかチェックしてくれました。とても小さな撮影隊でした。台湾ニューウェイヴ式です。
――ラストでラジオから流れるマレーシア語の歌はとても心に沁みますね。
冒頭でラジオ・パーソナリティ―になる夢を語る女性が出てきますが、彼女は最後にその夢を叶えたわけです。マレーシアの曲で映画を終わらせたいと思って、いろいろとネットで調べているうちにあの曲を見つけました。シーク教の神に捧げる歌で、新たな創造についての曲です。それがこの映画にとても相応しいと思いました。歌詞はとても興味深いものでした。ある種の理想主義が語られています。マレーシア社会には様々な宗教が存在し、互いに不寛容なところがあります。ある宗教を受け入れることとそれに対して寛容であることは違います。違いにばかり目を向けて、互いの類似点を見つけようとしないマレーシア政府の宗教政策には問題があると思います。私は様々なものを混ぜ合わせることに常に興味があります。
――監督自身が様々な国に赴いて、そこで映画を撮るというのが、その実践のように思います。
おそらく無意識にそうしているのでしょう。ヴェトナム、インドネシア、日本、シンガポール、タンザニアと渡り歩いていますが、次回作はついにマレーシアで撮るつもりです。
――次回作はどのような映画を撮ろうと考えていますか。
二つ企画があって、一つはシンガポール芸術祭からダンス映画を依頼されています。もう一つは私自身の企画です。ロッテルダム映画祭の基金で中国系マレーシア人についての映画を撮ろうと思っています。そちらの方はそれほど急いではいないので時間をかけて考えていこうと思っています。
(聞き手:葛生賢)
『燃え上がる木の記憶』