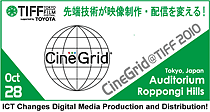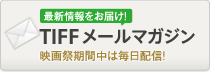2010.10.26
[インタビュー]
アジアの風『ハイソ』アーティット・アッサラット監督インタビュー(10/26)


©2010 TIFF
――「ハイソ」を製作するきっかけは?
「実は7~8年前から温めていた企画で、1作目に作るはずだったんです。でも、資金が調達できなくて、『ワンダフル・タウン』の方が(予算的に)作りやすかったので、この企画はしまいこんでいたんですね。でも、いつかはやりたいと思っていました」
――アメリカ留学からタイに戻り、映画俳優となる主人公は監督の分身のように映ります。
「100%そうですね。僕自身、アメリカでは外国人であって、タイに帰ってくるとアメリカンボーイと呼ばれて外国人扱いされ、どこにいても落ち着くところがない。アジア人としては西洋化しすぎているし、西洋人になるにはアジア人すぎるということです。そういうことを描いてみました」
――アメリカからタイに来た恋人と、徐々に気持ちがかみ合わなくなっていきますが、これは監督自身の体験ですか?
「はい。まさに、そういうことが起こりました(笑)」
――その後、新しいタイ人の恋人との関係も、もどかしいほどうまくいきません。そういう感情の機微がよく描かれた脚本でしたが、執筆の際に留意した点は?
「構成としては2つのパートに分かれていますよね。双方が合わせ鏡のように呼応する感じです。ラブストーリーの英語版とタイ語版といえるかもしれません。コンセプトは、どちらのケースでも恋愛関係が機能しないということです」
――2004年末のインド洋大津波で被害を受けた場所が、『ワンダフル・デイズ』に続きロケ地に使われていますが、その意図は?
「津波のときはバンコクに住んでいて、被害はタイの南部だったのでテレビのニュースで見ていました。1年後に被害を受けた場所に行ってみたら、すべてがきれいになっていてつめ跡が見られなかった。一見、何事もなかったように見えるけれども、人々の記憶からは消せないですよね。そういう部分が『ワンダフル・タウン』の着想の出発点になったんです。そして、1作目と2作目の間に何らかのつながりを持たせたかったので、『ハイソ』では俳優という設定で津波被害のあった場所で演じるということになったんです」

©2010 TIFF
――空港でのラストシーンは、あらゆる解釈ができますね。
「確かに何通りかあると思いますが、僕にとっては空港というのが重要。空港やホテルというのは国際的であると同時に、国籍がないともいえます。つまり、アナンダのように属する場所がない人にとってのよりどころ。僕自身が、空港やホテルで過ごすことが長い人生だったことを反映させています」
――今も自分がアウトサイダーだという意識はありますか?
「僕の70歳の父もアメリカで教育を受けて、僕と似たような育ち方をしています。その父でさえ、いまだにタイが自分の国という気がしないという。僕も一生消えないのかなと思っています」
――アピチャッポン・ウィラーセタクンが、今年のカンヌ映画祭でタイ映画として初めてパルムドールを受賞しましたが、刺激を受けましたか?
「同じインディペンデントで映画を作っている者として、彼の成し遂げたことがいかに大きいかはよく分かるので、とても刺激になりました。彼の意思、気持ちのあり方や、説得力のある映画を作るところに非常に敬意を表しています」
――監督2作目にして既に自分のスタイルを確立しているようですが、今後、興味をもっているテーマは?
「映画監督としてキャリアを築いていくこと自体が挑戦ですけれど、僕はまだ大勢の人をひきつける映画を作れていません。トニー・ジャーのような大衆がいっぱい見に来るような映画を作ることはないと思いますが、僕なりのスタイルでより多くの人に訴え、見てもらえるような映画は作ってみたいですね」
――2年ぶりの東京ですが、楽しめていますか?
「日本に来るのは大好きで、特に好きなのが温泉(笑)。それが一番楽しい思い出で、もう2回行きました」
異邦人であることを自認し、映画という手法で真正面から向き合っているアッサラット監督。淡々とした語り口は、彼の映像にも通じるところがあり、演出への確固たる信念が感じられる。「ハイソ」もまた、東京を起点に発信され世界へと羽ばたいていくはずだ。
(聞き手:鈴木元)
『ハイソ』

©Pop Pictures Co.,Ltd