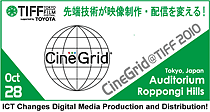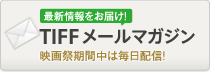2010.10.24
[インタビュー]
WORLD CINEMA 『ハンズ・アップ!』 ロマン・グーピル監督 インタビュー(10/24)

©2010 TIFF
――映画好きには神話的な存在として知られる監督の作品が、今回初めて日本で正式上映されて大変嬉しく思います。
私にとって小津安二郎の作品に描かれている日本の方が神話的です。彼の作品では、画面構成だけでなく、普通の人々が描かれている点が素晴らしいと思い、演出についても豊かで広がりがあることに感銘を受けていたので、今回初めて東京に来られて嬉しく思っています。

©2010 TIFF
――小津作品の普通の人々について語られましたが、監督の作品も普通の人々―ほとんど非職業俳優を使っていますけれども―に眼差しを向けています。
この作品では大人とは対極にある存在としての子供たちに、私の眼差しは向けられています。普通の大人たちについての眼差しは、必ずしも優しいものではありません。子供にとっては先生や警察官などあらゆる大人が脅威です。大人の側で何か上手くいっていないことがあり、そのためにミレナやその友達を排除しようとします。子供たちは大人の欠陥をそこに見ているのです。
――子供でさえも政治的な状況に組み込まれている。それが監督にとっての日常であるということでしょうか。
子供たちにとって大事なのは、相手がどんな国籍であろうと友達だったら大切にすることです。本質的なものを守っていこうとする態度が政治的であると言えるなら、そうでしょう。愛する人たちといかに一緒に生きるか、それは私たち自身が取り組まなければならない課題だし、しかも現実にはうまくできていない問題です。『三十歳の死』には、当時十四歳だった私が、世界を変革する企みのために地下室の入口に入るショットがあります。『ハンズ・アップ!』でも、無意識に全く同じ位置にキャメラを据えました。私は自分でも知らないうちに全く同じことを二世代後の子供たちにやらせていました。同じことをしなければいけなかったのは、それが全くうまくいかなかったということです。そのことを後で人に指摘されて気づきました。
――それらのショットから、『三十歳の死』から最新作に到るまで一貫する重要な主題が引き出せると思います。それは「グループをなすこと」そして「地下にもぐること」です。
私の映画では、グループは「いかに一緒に生きるか」を実践しようと試みる存在です。そのためにアパートや地下室に集まって、いろいろと企みをするわけです。閉じられた空間で夢を見るように仲間同士で「いかに一緒に生きるか」を考えていく。それがいつも表れているのだと思います。一般的には政治というのは下らないものだと思われがちですが、他者について考えるという意味で素晴らしいものだと私は思うし、映画はそうした問いを立てるものです。私の撮っているのは、いわゆる活動家的な政治映画ではなく、問いをたてるものとしての映画です。活動家が作る映画というのはそこになにか主張があり、一連のイメージを「ほら、これが解決策だよ」というふうに提示します。私はそういう作品を作りたいのではありません。私の最大の野心は、映画を見た人がその後に何かを考えるということです。皆で同じことを同じ瞬間に考えるのではなく、むしろある時に誰かが何かを考え、それから少し経って、また別の誰かがそれと自分の考えていることを結びつけたり、アイデアを発展させたりする。そっちの方に興味があるし、そういうふうになったらいいと思います。そのために私はいつもあるイメージを出したら、次にそれに矛盾するようなイメージを提示し、音に関しても矛盾があるようなものをあえて併置している。そうすることで一種の不確かさが生じ、観客も不安になってくるのですが、その不確かさがあるからこそ、そこから問いを立てられるのですし、そういうものを目指したい。ですから私にとって、疑いや不確かさ、そこにこだわるものが政治的な映画だと思っています。
――この映画の結末で二つのイメージが出てきます。少女が回想した「子供たちが手を挙げている」イメージと、そして少年が回想した「手を挙げていない」イメージ。これら二つのイメージを対置しているのは、それと関係があるのでしょうか。
まず彼女が回想した「私は誰が最初に手を挙げようと言ったのか覚えていない」という台詞があります。言い出したのは自分ではないということですね。そのすぐ後に少年が「そこに静寂があったことを私は覚えている」と述べます。実際にそのイメージを見ると、周りの人々が騒いでいたり、喜んでいたりする声が聞こえるので、少年が言う「静寂があった」というのも間違いです。そういう意味で二人とも言っていることが食い違いますよね。むしろ大事なのは「違う」ということであって、事件の後に振り返って物語を語る時、そこに差異が生まれてくることに注目したいのです。また手を挙げて出てくる子供について言えば、第二次大戦中のワルシャワのゲットーから手を挙げて少年が出てくるイメージがそこに重なっているということも考えられる。あるいは単に親にぶたれないように手で自分を守っていたのではないかとも考えられます。つまりひとつのイメージにひとつの真実が対応しているわけではない。また映画そのものが美しい嘘であるわけですから、そういう嘘に対してオマージュを捧げたいというのもあります。そんなわけであのようにイメージを対置させているのです。たくさんのイメージを対置させることから見えてくるものがあるはずです。その意味で私は映画を信じていますが、イメージを信じていません。
――あなたの『Lettre pour L…』では、マチュー・アマルリックが胸のところに「ただのイメージ(juste une image)」と印刷されたトレーナーを着ています。それは「正しいイメージなどない。ただのイメージがあるだけだ」というゴダールの言葉からの引用ですが、これら二種類のイメージの差異があなたにとって重要なのではないでしょうか。
「正しいイメージ(une image juste)」というのはゴダールの協力者であったジャン=ピエール・ゴランが言ったことですが、積極的な活動家であったゴランが「正しいイメージを撮ろう」と言った時、皮肉屋で矛盾好きだったゴダールは、むしろそれを疑うような態度をとったのだと思います。それは政治的な映画の中で常に問題となってきたことで、「ただのイメージ」というトレーナーを出すことで、「正しいイメージ」があるのかどうかという問題に対して、それをからかう意図もあったのです。『Lettre pour L…』以降、私にとって「正しいイメージ」というのが何なのか、ますます気にかかるようになってきました。ゴダールも「正しいイメージがあると思うのは危険だ」と考えているのだと思います。ゴダールに関していえば、もうひとつエピソードがあって、「なぜ映画を撮るのか」と問われた時、彼は「なぜという問題を避ける(eviter le pourquoi)ために私は映画を撮るのだ」と答えました。私はその意見に反対です。私は「なぜ」ということを追求するために映画を撮っているのです。
――「いかに一緒に生きるか」という問いは、外国人参政権問題が議論されている日本でも重要な問題で、この作品はそこに光を当ててくれます。
読書をしていると、あるひとつのフレーズに出会って自分が感じていたこととまさに同じことをそこに見出すという経験があると思いますが、それと同じようなことを私の映画で感じてくれる人がひとりでもいれば、これ以上嬉しいことはないです。「歴史に意味はない。そこにあるのは目を背けたくなるような惨事があるだけだ」と言ったユダヤ人思想家がいますが、しかし例えば、奴隷制のようにそれまで普通の人が自明だと思っていたようなことに対して、誰か一人でも異議を唱え、それが二人になり三人になりと続いていくことによって、歴史そのものも変えていくことができるのではないか、そこには崇高な意味があるのではないか。だから、もし今置かれている状況に自分でおかしいと思うことがあったら黙っていないで、「それはおかしい」と言うことで最終的に自分が目指しているユートピアを実現していくしか他に方法がないと私は思います。

©2010 TIFF
――今作は監督がこれまでやってきたことの延長線上にあり、それと同時により間口が広がっている作品だと思います。これを機会に監督の過去の重要な作品が日本でも公開されることを願います。
おっしゃる通り、確かに『三十歳の死』から今回の作品まででひとつのサイクルが閉じ、そこから新たなものが始まっています。ですから過去についての分析はひとまず終えて、これからはもう少し軽さのある楽しい作品を撮っていくつもりです。
(聞き手:葛生賢)
ハンズ・アップ!

©Les Films du Losange