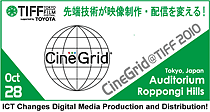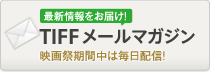2010.10.25
[インタビュー]
アジアの風『風に吹かれて―キャメラマン李屏賓(リー・ピンビン)の肖像』チアン・シウチュン監督、クワン・プンリョン監督インタビュー(10/25)


©2010 TIFF
――リー・ピンビンが世界有数のシネマトグラファーであることは誰もが認めるところですが、なぜ彼を対象にドキュメンタリーを撮ろうと思ったのですか?
チアン・シウチュン監督(以下 シウチュン): 10数年前にリー・ピンビンと知り合い、彼の人生経験と仕事に対する態度に啓発されたのがきっかけです。ホウ・シャオシェン監督のドキュメンタリーを撮りたいとずっと思っていましたが、なかなかその機会が得られず、リー・ピンビンについては本にしたいと思っていました。短編のドキュメンタリーを撮った時にクワン・プンリョンと知り合い、彼に「リー・ピンビンの本を作りたい」と言うと、「本ではなくドキュメンタリーにしたほうがいいんじゃないか」という意見が出ました。でもそれっきりになっていたのですがクワンが乗り気で励ましてくれたので、一層のこと本人に聞いてみようとなったのです。
――クワンさんは以前からリーさんと仕事上のつきあいがあったのですか?
クワン・プンリョン監督(プンリョン): ウォン・カーウァイ監督の『花様年華』の第2ユニットの撮影に参加し、リー・ピンビンも他のユニットのキャメラマンだったので、その時に知り合いました。でも当時一緒に仕事をしたわけではありません。その後、台湾で撮影の仕事をした時に、リー・ピンビンは素晴らしいカメラマンで若いスタッフにも助力を惜しまないと聞かされ、大変興味をもったわけです。たまたま香港に彼がいる時に話をし、彼の人柄に触れ、人間に対する細やかな愛情の持ち主だなと思いました。そして、この作品を撮る過程でもっと彼のことを知ることができました。細やかな愛情という点でいえば、人間だけでなくて、植物に対してもそうです。そうした彼の人間としての感情が、映像を通して観客に深く訴えるのではないかと思います。
――映画の中のリー・ピンビンを観ていると、外見はオオカミみたいなのに目はとても優しそうで、話す言葉には鋭敏な感性がきらめいています。こうした外見と内面の要素もあって、創作意欲を掻き立てられたのかと思ったのですが。
シウチュン: 仰るとおり、すごく魅力のある方で、彼自身の美学もまた分け与えるに値すると思ったのが、本にしたいと思った最初の動機です。私は作家ではないので、誰か筆の立つ人に書いてもらえればそれでいい。とにかく彼のことをもっと知ってもらいたいという思いでした。だから当初は自分で撮らなくても、そうした作品があれば観たいなと思っていたわけです。でもやはり自分でやりたいと思い立ったのは、ホウ・シャオシェン監督とも親交があり、リー・ピンビンとも長いつきあいあったからです。
――クワンさんはこれまでにも多くの映画監督の撮影に携わってこられましたよね?
プンリョン: スタンリー・クワン監督の作品に2本関わり、うち1本はドキュメンタリー作品です。ウォン・カーウァイ監督の作品には様々なかたちで関わり、『欲望の翼』(90)の頃から参加していて、『楽園の瑕』(94)の撮り直しも私がやりました。『2046』(04)、『マイ・ブルーベリー・ナイツ』(07)の撮影にも参加しています。
――クワンさんは香港と台湾の双方で活躍されてますが、映画人同士の交流は盛んなのですか?
プンリョン: リー・ピンビンは例外的に香港で仕事をしたし、録音技師で言えば杜篤之(ドゥ・ドゥージ)のチームは香港でもよく仕事をしていました。それ以外に、台湾と香港ではあまり交流はなかったと思います。
シウチュン: クワンは台湾でもよく撮っていて、今回の映画祭で上映される『ズーム・ハンティング』も彼の撮影によるものです。
――チュアンさんは『枯嶺街少年殺人事件』(91)に出演され、その後、ホウ・シャオシェン監督やエドワード・ヤン監督の下で働いていたとのことですが、お2人の影響みたいなものはありますか?
シウチュン: エドワード・ヤン監督は私を映画の世界に導いてくれた恩師です。その後ホウ・シャオシェン監督と仕事をしましたが、2人から得たのは映画という仕事への態度だったと思います。自分に対してすごく厳しい要求を課すところなど、大いに影響を受けていました。でも映画の作風という点では世代も違うし、私自身の好みも2人とはまったく違うものでその点での影響はないと思います。
――2人で1本の作品を仕上げるにあたって、どのように役割分担されたのですか?
プンリョン: 私はキャメラマンで、演出の経験があるわけではありません。チアンも監督としてそれほど経験があるわけではないので、役割分担などは考えず勢いで進めていきました。まだ資金が出るかわからない時期に、『ホウ・シャオシェンのレッドバルーン』の撮影がフランスであると聞いて飛んで行ったり、チアンに子供が生まれることになって中断したり。そしてまたリー・ピンビンがノルウェイで賞をもらうことになり、同行したりということの繰り返しです。ふだんはチアンがインタビュアーで、私はキャメラマンを務めていましたが、ノルウェイにはリー・ピンビンの母親が来てチアンがエスコートしていたので母親を撮る時には彼女がキャメラを務めました。
シウチュン: でもこの作品が好評だったのは、クワンの撮った映像のセンスの良さがあったからだと思います(笑)。
――ナレーションを入れたりという全体の構成は2人で考えたのですか?
プンリョン: 3年もかけて撮りためた映像があったので、それを少しずつ段階的に編集し、どんなふうに並べていくかを考えました。冒頭のナレーションは私がやり、終盤の女性の声は彼女のものです。
シウチュン: ナレーションは2人が書いたものですが、映画の最後に朗読されるのは、ノルウェイで賞をもらった時のリー・ピンビンの言葉です。
(聞き手:赤塚成人)
『風に吹かれて―キャメラマン李屏賓(リー・ピンビン)の肖像』

©Yonder Pictures Limited Inc.