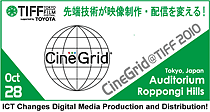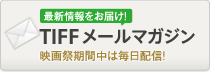2010.10.23
[イベントレポート]
「ドキュメンタリーとフィクションの間に線引きをすることには、あまり意味がないと思っています。」-10/23(土)『燃え上がる木の記憶』シャーマン・オン監督:Q&A

今年の東京国際映画祭 アジアの風の最初の上映となったのは、マレーシア出身の現代美術作家であり、気鋭の映像作家でもあるシャーマン・オン監督が、タンザニアの首都=ダルエスサラームで撮影した「アジアの風景や、アジアの俳優が登場しない」新しいアジア映画『燃え上がる木の記憶』。
オン監督の前作『はし/hashi』(08)は福岡で撮影されたということもあって、会場には監督の“日本の仲間”も多数ご来場。なごやかなムードの中、石坂健治 アジアの風 プログラミング・ディレクターの司会でQ&Aがスタートしました。

©2010 TIFF
※記者会見の内容には、作品内容に触れている箇所がございます。ご注意ください。
まずは、監督から観客の皆様へのごあいさつ。
この作品は、ロッテルダム映画祭の「アフリカをはじめて訪れた映画作家が、どのような印象を抱いて、その地で映画作品をつくりあげるか?」という企画で製作されたもの。アフリカのどの国を訪れるかは監督に一任されており、政治的に安定していること、そして「アフリカにありながら、インド人が強い力をもっており、アラブ文化の影響も大きい」タンザニアの多様性が、監督の母国マレーシアの多民族性に近いものを感じたため、この国を舞台に選んだこと。
出演者オーディションを行ったところ、プロの俳優はオーバーアクトの傾向が強すぎて(監督の弁によると「タンザニアはナイジェリアの影響が強い国で、そのナイジェリアは“ナリウッド”と称されるほど商業映画の産業が盛ん。そのため、タンザニアの専業俳優はエンターティンメント性が強すぎる」らしい)、結局、町で出会った一般の方々に出演をお願いすることになったということ。
作品はCANONのEOS 5D Mark II を使用した、日本でも注目されている“デジタル一眼ムービー”であり、アシスタントはダルエスサラームの大学生3人が担当したこと。
先にキャスティングを決めて、彼らひとりひとりにインタビューをし、そこから導き出される彼らのストーリーをベースに脚本をつくるという、ドキュメンタリーとフィクションの境界線を飛び越えたような作劇スタイルであったこと。
監督が出演者に求めているのは「演じるテクニック」ではなく、彼ら自身の「生」の部分であって、監督が彼らを信頼すればするほど、ミラクルな何かが返ってくることを信じているということ。
といったさまざまなお話を、流麗な英語でスピーチされました。
続いて、場内のお客様からのご質問。
Q1:映画のラストに流れるマレーシアの歌は、映画用のオリジナル曲ですか?
シャーマン・オン監督:「この曲は、インターネット上で見つけました。マレーシアの多様性と、その理想が込められたような曲で、本作にぴったりだと思います。」
Q3:映画の前半ではタイトなフレームのショットが多く、後半になると一転、ワイドショットが印象に残りました。この“使い分け”には、どのような意図があったのでしょうか?
オン監督:「映画の前半は狭い場所での撮影が多かったため、たまたまそうなってしまったんだと思います。僕は標準レンズの画が好きなので、今回は全編50ミリの短焦点レンズを使って撮影をしています。」
Q4:アマチュア俳優とのコラボレーションで、何かエピソードは?
オン監督:「タンザニアの方とは本当に色々なお話をしたんですが、とくに印象に残っているのが、宗教に関するお話です。
彼らは、結構簡単に宗教を変えることがあるそうなんですね。例えば、教会の近くに引っ越したんでクリスチャンになる、みたいな。マレーシア人の僕にとっては信じられないことなんですが、それだけに興味深い。そんな感じでエピソードが50くらい集まったんで、長編をつくることができました。
僕は、ドキュメンタリーとフィクションの間に線引きをすることには、あまり意味がないと思っています。ペドロ・コスタやヴェルナー・ヘルツォークもそうですが、映画を撮っているときに、いま目の前にある現実を体験することが重要なのではないでしょうか。」
Q5:劇中、呪術医のエピソードが出てきます。これは、アフリカの宗教を表現する上で効果的なテーマではないかと思いますが、あまり深く掘り下げなかったのは何故でしょうか?
オン監督:「例えばサファリの大自然のような、アフリカの典型的なイメージには興味がなかったんです。タンザニアの、リアルな現実を描きたかったんですね。この『燃え上がる木の記憶』は世界中の人に観ていただいているんですが、その中にタンザニアで生活された方がいらっしゃいまして、彼に「まるでタンザニアに帰ってきたみたい」といっていただけました。これはとてもうれしかったです。
もちろん、呪術医という存在がタンザニアの現実生活に根ざしていることは間違いないのですが、それを誇張するのではなく、日常の中にちょっと独特な(非日常的な)要素が介在してくる、そのハーモニーというかバランス感覚を、ちゃんと表現することに注意しました。」

©2010 TIFF
『燃え上がる木の記憶』

→作品詳細