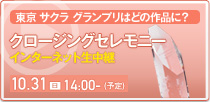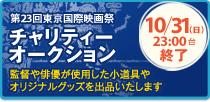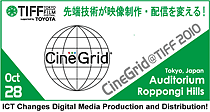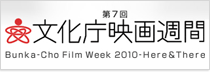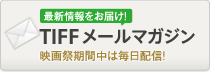2010.10.29
[インタビュー]
アジアの風『海の道』シャロン・ダヨック監督、リリト・レイエスさん(プロデューサー)、マリア・イザベル・ロペスさん(女優) インタビュー(10/29)


©2010 TIFF
――『海の道』は、監督の故郷で密航が行われているという現実が、製作の大きな動機となったのでしょうか?
シャロン・ダヨック監督(以下 ダヨック): そうです。私の故郷は、密航者が出発する場所であり、マレーシアを国外追放になった人が戻ってくる場所でもあります。2002年ごろから取り締まりが厳しくなって国外追放者が増え、大きな船に詰め込まれて酸欠になったり、食糧がなくなったりして亡くなる人も多かったんです。そういう問題に取り組んでいる弁護士に、いろいろと事実を教えてもらいました。この映画は実際にあったケースを基に作ったものです。

©2010 TIFF
――これまではドキュメンタリーを撮っていますが、今回、劇映画にしたのはなぜですか?
ダヨック: ドキュメンタリーで考えていたのですが、そのためには密航者と同じ船に乗って国境を越え、マレーシア領域に入らなければいけない。それはあまりに危険で不可能なので劇映画にしたわけです。でも、同じメッセージを観客に感じてもらうことはできると思っています。
――プロデューサーとしては、どのように製作を進めていったのか?
リリト・レイエス プロデューサー: (フィリピンの若手監督の登竜門とされる)シネマラヤ映画祭から100万円の助成を受けましたが、それだけで映画を完成させるのは不可能。途中で資金がなくなりましたが、フィリピンにとって切実な問題を誠実に描いている映画なので、必ず完成させたかった。だから、CMの制作会社にいる友人たちに頼んで、音響や音楽などを無料でやってもらったこともありました。

©2010 TIFF
――フィリピンのトップ女優であるマリアさんは、どこに魅かれて出演を決意したのですか?
マリア・イザベル・ロペス(以下 ロペス): シャロン監督の名前は知りませんでしたが、若いけれど生意気ではない(笑)、とても有望な監督だと分かりました。そして脚本を読み、本当にこれは大事な映画、多くの人に知ってもらうべき映画だと思ったのです。

©2010 TIFF
――不法滞在者の中には口を固く閉ざす人も多いと思います。リサーチは大変だったのでは?
ダヨック: 国外追放に遭い、戻ってきた人の話を随分聞きました。そういう人たちが一時収容されるセンターがあり、口の固い人もいましたけれど、ソーシャルワーカーを介して私が聞きたい質問をリストにして渡せば、コミュニケーションが円滑にいくようになったんです。中には、自分たちがどれほど大変な目に遭ったかを話したくてしようがないという人もいました。それら聞いたすべてを取り入れて脚本にした結果が、『海の道』です。
――フィリピンにとっては繊細な問題です。周囲の批判やバッシングもあったのでは?
ダヨック: 密航者すべてがザンボアンガの人間ではなく、他地域からもたくさん来ています。ですが、強制送還された人たちが戻ってくると、彼ら全員を匿って住む所や食べ物や交通費を提供したりする費用をすべて自治体が負担しなければなりません。そういう経済的な理由で、ザンボアンガの市長は国外追放者を受け入れることを良しとせず、むしろ多くの人に知ってもらいたいと思っていたので、とても協力的でした。
――海上で夜間の撮影が多く、大変だったのでは?
ダヨック: 船の内部で撮るシーンは、唯一の光源はランプです。それが数時間で消えてしまう。しかも、4時間ですべてを撮る必要がありましたのでとても大変でした。
ロペス: マングローブ林でのシーンは、足元が泥沼のようで、長靴が抜けなくなってしまうほど。長靴から足が抜けてしまったところを、ウミヘビにかまれた人もいました。常に救護隊がいてくれましたが、本当に怖かったですね。

©2010 TIFF
――いろいろと困難はありましたが、完成させられたことですべて報われたのでは?
ダヨック: キャストもスタッフもとても熱心に頑張ってくれて、支えてくれたので自分はとてもラッキーだと思っています。予算も少なくロケも大変でしたが、最後には皆がとても楽しかったと言ってくれました。大きな挑戦でしたが、素晴らしい経験ができたと思っています。
――東京国際映画祭で上映された感想は?
ダヨック: 問題は、なぜフィリピン人がそれだけのリスクを犯し、先のことも見えないまま不法滞在をしなければいけないのか、フィリピンの何が彼らを駆り立てるのか、それを見るべき必要があります。釜山にも行きましたが、アジア各国で上映されることはとても意義があります。東京での上映も素晴らしい体験でした。
(聞き手:鈴木元)
海の道

©Los Peliculas Linterna Studio