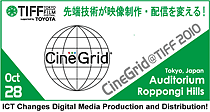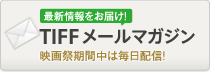2010.11.01
[インタビュー]
コンペティション『僕の心の奥の文法』ニル・ベルグマン監督、オルリ・ジルベルシャッツさんインタビュー

両親とも新世代の若者とも相容れない繊細な心を持つ少年アハロンは、大人になることを拒むように成長することをやめてしまう。ベルグマン監督とアハロンの母親を演じたオルリ・ジルベルシャッツさんにお話をうかがった。

©2010 TIFF
――家族は社会の縮図と見ることもできますし、個人の内面を掘り下げるのにも有効だと思いますが、監督はなぜ前作につづいて家族の物語を選択したのでしょうか?
ニル・ベルグマン監督:この映画は、ホロコーストが二度と起こらないように新しい国家を築こうという意気に燃えていた時代に設定されています。当時はとにかく力を持つことが第一義でしたから、繊細でアーティスティックな魂を持った人たちには居場所がありませんでした。私はいつも国家や社会を描くためには、個人の物語を語ること、家族のなかでの関係というものを見せるのが有効だと思います。
私自身が機能不全に陥った家族の物語にとても引かれるということもあります。また同時に、大人のルールに縛られる前の子供時代を描きたいと思いました。この年代の子供は周囲の様々なことに疑問を持ちますね。主人公のアハロンが持つような疑問というのは、現在のイスラエルに暮らしている人たちがもう考えなくなった疑問なんです。国家が強くなることばかりに尽力しているからです。
この映画は、自分とは異なる者に対する共感や優しさを訴えていると思います。家族のことだけではなく、イスラエル人とパレスチナ人が生活している地域全体で、お互いに違うものを受け入れるべきなのではないかというメッセージを強く発していると思います。

©2010 TIFF
――この映画では一方に、青年団の輪をくぐる試練やバル・ミツワー(成人式)など個人が集団に加入する儀式があり、もう一方ではアハロンが、脱出王フーディーニを真似て脱出への挑戦を繰り返し、また隣人の女性エドナの部屋に忍び込み、隠れ家にしていきます。
ニル・ベルグマン監督:アハロンは、他の子供と同じようにすることができない子なんですね。内面に何か違うものを持っている。だから自分が特別な人間であるということを感じとる必要がある。そしておそらく特別な人間に、たとえばアーティストになるのではないかと私は思っています。そういうわけで、焚火の試練の場面でも、人の輪を二回くぐらなければならなくなるのですが尊大だとみなされて罰を受ける。彼の人生にはあのような罰がずっとつづくと思います。俯瞰で撮った最後の独立記念日のシーンで、彼がいつの間にか全然違う集団のなかに入っていることにお気づきになったでしょうか。アハロンは、この国でどうすれば生きのびていけるのか、自分で答えを見つけるしかないのです。
――アハロンの隠れ家になるエドナの部屋には絵画や本が並んでいましたが、窓外の木が切り倒され、壁が壊され、ピアノが売られ、最後にはまるで爆撃の跡のように見えます。それは社会の一面を象徴しているように思えたのですが…。
ニル・ベルグマン監督:いまおっしゃったことは完璧な解釈になっています。あれは文化の死を意味しています。エドナは文化や芸術を象徴していて、アハロンにとってはあそこだけがそういうものに触れられる場所でした。でもエドナがアハロンの父に愛されたくて、壁の取り壊しを頼みあのようになっていきます。戦争というのはそれ自体を体験するだけではなく、他のものも壊してしまい、第二のトラウマを生みだします。エドナはまさに第二のトラウマに襲われ、愛も得られません。私が観客に最後に感じてもらいたかったのは、家族がそろって豪華な夕食を食べていても、戦争の影は決してなくなっていない、過去は彼らとともにあるということでした。
――ジルベルシャッツさんは、母親をどのように解釈して演じたのでしょうか。
オルリ・ジルベルシャッツ:とても意地が悪くて攻撃的な母親ですが、彼女はホロコーストの生存者です。当時の人々は、とにかく生きのびるだけで精一杯でした。だからアーティストのような魂を持つ子供にどう接していいのか見当もつきません。母親にしてみたら、将来のことが心配でたまらないわけです。もし社会から少しでもはみ出すことがあれば、ろくなことにはならない。だから逞しい男にしなくてはという強迫観念に駆り立てられているのです。

©2010 TIFF
――前作にも出演されていますが、監督との仕事は、あなたのキャリアのなかでどんな位置を占めているのでしょうか?
オルリ・ジルベルシャッツ:私たちは長年の友人です。ニルは私のなかから自分でも気づいていない力まで引き出してくれる監督で、私は彼を全面的に信頼しています。今回の映画は大きな挑戦でした。前作が成功を収めたので、同じようなやり方で作ればまた成功するのではないかという誘惑があるわけですが、私たちはそれは避けるべきだと思いました。もし完璧なものができなくても、新しいものに挑戦したのだと納得できるようにこの母親を演じました。
英語を勉強中のアハロンは、“現在進行形”に特別な関心を示す。仲間たちは子供時代を“過去”のものとして切り捨て大人になっていくが、彼はそれを拒む。ベルグマン監督も何かを切り捨てるのではなく、過去と現在、戦争と日常、自己と他者の関係などを現在進行形的に再構築してみせる。そんな奥深い世界を切り拓いた作品が、8年を経て今年の“東京サクラ グランプリ”に輝いたことを心から祝福したい。
聞き手:大場正明
『僕の心の奥の文法』

©Libretto Films - Norma Productions