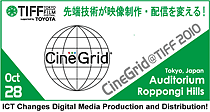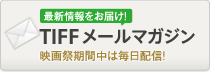2010.10.29
[インタビュー]
コンペティション『ブライトン・ロック』ローワン・ジョフィ監督インタビュー(10/29)


©2010 TIFF
――10年くらい前にお父さんのローランド監督にもインタビューさせていただいたことがあるのですが、ローワン監督が映画の道に進まれたのはお父さんの影響もあったのでしょうか?
監督:ある意味ではそういえます。ただ、父が監督だったので自分も監督になりたいと思ったわけではなく、父親が監督だからこそ自分は監督になりたくないと思い、脚本を手がけるようになりました。それで、父とは違うことをやっているという信念をもって10年くらい脚本を書いてきたのですが、そうこうしているうちに自分の脚本を他の人が監督することに物足りなさを覚え、だったら自分で監督しようと思うようになりました。
――映画では設定が30年代末から、1964年に変更されています。監督は1972年生まれなので、60年代を直接体験してはいませんが、この時代をどのように認識していたのでしょうか?
監督:私はまだ生まれていませんでしたが、まさにその時代を生きた両親に育てられ、子供の頃から60年代の価値観や言葉に触れていました。たとえば私の母はフェミニストで、父はたぶん労働党に入って活動していたのではないかと思います。ですから60年代はとても身近で、その時代を簡単に想像することができました。脚本を書き上げた段階で、プロデューサーのポール・ウェブスターや、『さらば青春の光』に出演していたフィル・デイヴィスに台詞などをチェックしてもらい、大丈夫だといわれて安心しました。フィルは今回の作品にも出演してくれました。
――原作のピンキーは、セックスを嫌悪する童貞の若者で、両親のセックスを見たことがトラウマになっています。時代を60年代に変更するにあたって、ピンキーについてはどんな若者をイメージしていたのでしょうか?
監督:とても興味深い質問です。いいのか悪いのかわかりませんが、いまの子供は両親のセックスを見てしまってもトラウマにはならないのではないかと思います。私自身もたまたま見てしまったことがありますが、サイコパスにはなりませんでした。ですから、そういう原因では説得力がない。そこで思い出したのが映画『ザ・ビーチ』です。
私はアレックス・ガーランドの原作が大好きなんですが、映画の脚本は、「ぼくの名前とぼくがタイにいること以外あなたは何も知る必要がない」というような台詞からはじまります。今回のピンキーもまさにそれだと思いました。つまり、観客がピンキーについて知るべき唯一のことは、彼があらゆる人を憎んでいるということだと。なぜなら彼はあらゆる人を恐れているから。憎しみは恐れからきている、それだけで十分だと思ったわけです。というのも、この社会のかなりの部分が恐怖心から成り立っているからです。

©2010 TIFF
――この映画には、『さらば青春の光』と同じようにモッズとロッカーズの対決があり、それがピンキーの特殊性を際立たせています。上の世代に反抗するという点では同じですが、モッズやロッカーズがグループで行動するのに対して、ピンキーは常に孤立しています。彼はより現代的な存在で、監督は彼を通して現代を表現しているように思えます。
監督:そういうふうに言っていただいてとてもうれしいです。“モノマニアック”ということですね。この言葉は、自己中心的でとにかく人と接することができない、相手が自分の目的に利用できる場合以外は、すべての関係を排除するような人間を意味するのですが、ピンキーはまさにそれだと思います。だからグループに属せないし、属したくもない。考えてみると、私たちはお互いが信じられなくなるようなパラノイアの時代に生きています。気をつけないと、私たちが向かっている世界をピンキーが表しているということになりかねません。

©2010 TIFF
――原作のローズはイノセントな存在で、背景にはカトリックの信仰がありますが、映画のローズについてはどのように解釈していたのでしょうか?
監督:最初の映画化(1947年)のときには、彼女は単なる受身的な犠牲者として描かれていたと思うんです。原作ではある意味、聖人として描かれている。とてつもない苦難を受け入れて、それに立ち向かうのが聖人であり、それが彼女だと思ったわけです。この映画では60年代に設定したことによって、自分の運命に対してよりアクティブな女性になっています。ピンキーは彼女の父親に会って、お金を払って結婚の承諾を得るわけですが、その前のところでピンキーが、それで何を得るのかとローズに尋ねると、彼女は人生だと答えます。あれは原作にはないやりとりで、私は誇りに思っています。彼女は率先して自分の運命を切り拓いていくということです。
ローワン・ジョフィ監督の次回作はすでに動き出している。新人作家S・J・ワトソンのサイコロジカルなサスペンス小説「Before I Go To Sleep」(2011年出版予定)の映画化だ。『ブライトン・ロック』を気に入ったリドリー・スコットがプロデュースを手がけているという。ローワン監督がサイコロジカルな要素をどう料理するのか注目したい。
(聞き手:大場正明)
『ブライトン・ロック』
→作品詳細