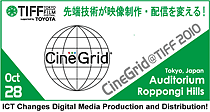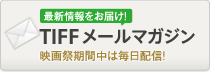2010.10.29
[インタビュー]
natural TIFF supported by TOYOTA 『水の惑星』ケヴィン・マクマホン監督インタビュー (10/29)


©2010 TIFF
――五大湖は壮大なテーマですが、どうしてこのテーマを選んだのですか?
私の初長編監督作は“The Falls”でナイアガラの滝についての作品です。あの地域のリポーターとして仕事をしていたからです。私はずっと水の問題に興味があり、水に関する映画をまた作りたいと思っていました。河川や海には公害があり、また外来種の侵入もあります。どれをテーマにとっても作品ができるでしょう。この作品もトロント湾だけに限定してもひとつの作品として成り立ったかもしれません。世界中の湾が抱えている共通の問題がたくさんありますから。ジャーナリズムの手法ではそれらを問題として提示すればいいのですが、映画として観客の感情に訴えるものを作るならば、物語を見つけなければなりません。”Paddle to the Sea”という古い子供向けの本があり、50年前にNFB(National Film Board of Canada)によって映画化されました。そのアイデアを拝借したわけです。ネイティブアメリカンの子供がカヌーを作り、スペリオル湖から漕ぎだし、五大湖をすべて抜けて大西洋までたどり着く物語でした。そのストーリーを借り、カヌーではなく、川に沿ってたどろうと考えたのです。結果的に、映画に登場するネイティブアメリカンの女性―五大湖の周りを歩く旅をしている―に出会うことになりました。
――あの女性の旅は、時間がかかったでしょうね。
6年かかりました。撮影を始めた当初は彼女のことを知りませんでした。作品にストーリーをもたらしてくれる人に出会えたのは運命的でした。つまり、ある種の作られた物語ではあります。マイケル・ムーアがやっていることと同じです。彼は保険制度や財政問題を取り上げたいと思ったら物語をでっち上げるわけです。「GMのトップに会いに行く」とか「彼らをキューバに連れていく」とか。そうすることで、感情移入できるようにするのです。
――マイケル・ムーアとは違って、あなたの作品は特に敵対的ではありません。
そうすることもできたとは思います。もしかしたらそのほうが賢明で、映画としては売れたかもしれません。現在のメディアが知る唯一の報道手法ですからね。私がジャーナリズムを学び始めたころにその手法を教わりました。それがマイケル・ムーアが取っている手法であり、ヒット作にする方法なのでしょう。皆、正義の戦いが好きですから。でも私にとってはどれほど糾弾すべき問題があろうと、攻撃すべき企業があろうとも、水というのは集合的な物語なのです。特定の誰かを非難するのは間違いです。誰をつるしあげればいいのですか? この水域には、4千万人の人間が住んでいます。私は常套手段を使いませんでした。残念ながら、私は公平な精神の持ち主ですから、私の作品はマイケル・ムーアの作品ほどヒットしません(笑)。

©2010 TIFF
――バランスには注意が必要ですね。あなたの作品ではナレーションはすべて匿名ですが、行政側に立つ主張に対しては反論を提示していますね。
ナレーションの入れ方については批判もあります。「真実を言っているかどうか分からないじゃないか」と。それも一理ありますが、でもやはりこれは集合的な物語なのです。様々な意見が行ったり来たりします。この作品では環境を守るヒーローは登場しません。ネイティブアメリカンのジョセフィンはそうかもしれませんが、彼女は実際には幻想的な旅をしているだけです。作品で出てくる二つの対立意見は、「我々は本当にひどいことをしてしまった。水は汚染されている」そして、「ああ、水はキレイだな」というものだと思います。その両意見の間を行ったり来たりする。それ以外のことはすべて人間の愚行です。私たちは愚かなことをした結果、汚水だめの周りで暮らすことになった。そのことに対して何をすべきなのでしょう?
――作品の中で、誰かが湖は「感情面の支え」にもなっていると言っていました。それはどういうことなのでしょうか?
どの文化にもあることです。山に行ったり海に行くことは、文字どおり休養です。私が思うにその話者が意図していたのはそのことだと思います。水の中で遊ぶ子供のスローモーションでの映像や風景を撮った映像が示しているものです。水辺にはまだ多くの美が存在していることを再認識しようと試みました。そうすることで人々に湖は保護するに値するものだと分かってほしかったのです。それが最大の目的です。単に「人類がひどいことをして、水を汚染した」―それは真実なのですが―それだけを非難しているわけではありません。保護する価値のあるものだという考えをアピールしているのです。
――シカゴ川をカヌーで下る男性が出てくるシーンもそうですね。川は汚れきっているが、それでも水路として活用し楽しんでいる人々がいる。
彼らは、川ではカヌーくらいできないといけないということを証明するために、川下りをしています。誰もシカゴ川でカヌーをしたいとは思いませんが。ひどい臭いですから。
――この映画には数多くの厳しい事実が明るみにされています。通常のドキュメンタリーというよりも教育的な映画という印象が強いのですが、その点はいかがですか?
それも役割のひとつだと思っています。自分はジャーナリストだと思っていますので、人に何かを知らせる欲求は持ち続けています。映画祭への出品は喜ばしいことですが、最終的にはこの類の映画は教育分野に受け継がれるものだと思います。学校や公共団体などで上映されると思います。五大湖の環境問題に取り組む団体を統括する大きな組織があり、メッセージを周知させようと努力しているのですが、外来種の問題などを説明するのは彼らにとって難しいのです。ですので、この映画を上映することでその役割を担える。春にシカゴで上映が予定されています。ロバート・ケネディ・ジュニアが主宰を務めるWaterkeepersという団体があって、北米の全水域にそれぞれの保護団体を発足させるために活動しています。彼らはこの映画を上映してアジア鯉の問題を説明したがっています。映画の中で示しているように、この外来種は五大湖に向かっていて、もし侵入してしまったら生態系への甚大な問題に発展してしまいます。
――鯉がボートや網に飛び込んでくるシーンは非常に効果的でしたね。いかに攻撃的な種であるかを顕著に示しています。
信じられない光景です。この映画を作ったことで、(鯉を妨げるための)電気バリアが機能していないことが分かったのです。そしてミシガン湖でアジア鯉のDNA―卵とうろこのものですが―を捜索しはじめました。警鐘は鳴らされたのです。裁判でも係争中です。五大湖周辺の8州のうち7州がイリノイ州とシカゴ市に対し川を封鎖し外来種の侵入を防ぐよう申し立てています。裁判は今も続いています。裁判所や議会や集会に問題を提示したくても簡単にはいきません。何らかの視覚的資料がないと問題の本質が伝わらないのです。ですから私は自分の役割を起こっている問題の証明を提供することだと考えたわけです。五大湖周辺で発行されている新聞を読めば、映画で語られていることは目新しいことではありません。しかし、何十もの上映会に参加しましたが、皆「知らなかった」と言うのです。おそらく新聞を読まないからか、あるいは映画でひとまとめにしたものを観て初めて心に響いたのかもしれません。
――だから基本的な知識を説明するためにアニメーションを使ったのですか?
これは芸術映画なのか科学映画なのか分からないと批判する人もいました。私自身はアニメーションの部分は美しいと思いますが、いずれにせよ川に毒を廃棄することがどういうことになるのかは、分子レベルで起きることを実際見ないと理解できないと思います。双頭の子供が登場すれば分かりやすかったかもしれません。サリドマイドや水俣病など観客の直感に訴える効果のある事例があれば、別の方法を取ることができたかもしれません。
――汚染によるホルモンバランスの異常でオスのカエルがメスになってしまったということを視覚的に示すのは難しいですね。見た目は同じですから。
そうです。20年前と現在でDNAが変化したことをどう提示できるのか。汚染物質というものはそういうものです。人類が真剣に考えなくてはいけない問題です。そのために何とかして描く手段を見つけなくてはならないと思いました。

©2010 TIFF
――この映画による効果は出てきていますか?
周辺住民は危機感をもったようです。そのエネルギーを集約するウェブサイトを立ち上げました。ひとつは子供たちへの教育目的のもので、もうひとつはWaterkeepersや他の環境団体と連動するものです。「何をすればいいの?」と言われれば、「ウェブサイトに選択肢が載っているよ」と答えます。実際活用されています。最終的には政治的な動きを目指しています。すべての環境問題はインフラ整備と不可分です。社会の膨大な消費資源と焼却物や排泄物が本来行くべきでないところに廃棄されている。しかし立法上の変化はまだありません。
――五大湖は国境をまたいでいます。そのことはこの問題に影響していますか?
複数の司法権が関わるといつも問題は放置されがちです。カナダとアメリカ合衆国政府があり、そしてすべての合衆国州政府と2つのカナダの州政府が関係している。カナダ人は自分たちの美徳をもち、合衆国は良き身内だと考えている。だが実際には、科学調査や行政措置や美化に対する努力において、アメリカ人のほうが五大湖により深く関わっている。しかし問題は海と同じ。海が汚くなったら人々は、「私たちのじゃない。下流のずっと先の人たちの国の問題だ」と言ってしまう。世界のどこでもね。
――最後はシロイルカがガンで死んでいっている話題になり、証明できる関連性がないから誰かを非難することは難しいと指摘していますね。
そうです。そしてその関連性を示すのがこの映画の狙いです。作品の中でひとりの男性が「この病気は化学物質が原因だとはいえない」と言っていますが、実際このシロイルカの場合はエリー湖あるいはオンタリオ湖にしかない毒素によるものだと証明できます。しかし確固たる関連性ではない。科学者は相関関係はあるが、それが必ずしも因果関係とはならないと述べています。分かりやすい例が気候変動です。誰もが直感的に気候変動が起きていて、おそらく人類のせいだろうと思っている。そこでどうなるかというと、誰も犠牲を払いたくない。もし石油化学企業の人間なら、「証明しろ」と言うでしょう。科学者を押しのけて“詩人”が幅を利かせるのです。結局、この種の問題の解決策は政治的なものになり、その政治的解決の原動力は科学的根拠よりも感情論にもとづいてしまう。合理的な流儀に則って議論されたケースはありません。私は合理性を信頼したいが、電子メディアの世界には合理性が成立するまで待って仕事する観点はありません。感情的な内容にするかどうかは伝える側次第。プロパガンダを作りだしてしまう可能性もある。それはイヤでしょう?
――それは芸術か科学かという議論に戻る話ですね。もし美術効果を使って議論を展開しようとすれば、人から「何をやっているんだ、なぜ直接的に問題を指摘しない」と言われてしまう恐れがあります。
そこが試練のしどころです。合理的に成り立つ十分な証拠を入れ込みたいが、複雑な科学は理解できない。多くの工場で撮影を拒否されました。唯一許可された製紙工場は、河川に流れ出た廃棄物の90%は回収しているという事に誇りを持っていて、実によいことだと考えています。でもそれを聞いた私や観客は“じゃあ残りの10%は?”と疑問が浮かぶ。そこで皆さん自身が結論を導く必要が出てくるのです。
(聞き手:フィリップ・ブレイザー)
『水の惑星 ウォーターライフ』
→作品詳細