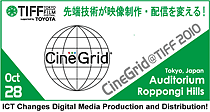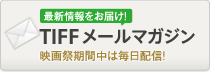2010.10.29
[イベントレポート]
リー・チーガイ監督、スー・チャオピン監督、栗山千明さんが種田陽平を絶賛!─10/29(金)映画人の視点「映画人、種田陽平の世界」

23日(土)の小泉今日子さんに続いて、29日(金)の登場したのは、美術監督の種田陽平さん。岩井俊二監督(『スワロウテイル』)、三谷幸喜監督(『ザ・マジックアワー』)、クエンティン・タランティーノ監督(『キル・ビル VOL.1』)ほか数多くの映画監督の作品を手掛け、今年はスタジオジブリの『借りぐらしのアリエッティ』とのコラボレーション「借りぐらしのアリエッティ×種田陽平展」を成功させるなど、実写/アニメ、そして日本国内/国外を問わずに活躍し続ける美術監督です。

©2010 TIFF
今回上映された作品は、リー・チーガイ監督の『不夜城』、スー・チャオピン監督の『シルク』、そしてタランティーノ監督の『キル・ビル VOL.1』の3本。上映前には各作品ゆかりのゲストが迎えられ、興味深いエピソードが綴られました。
最初に登場したのは、映画プロデューサーの河井真也さんと前田浩子さん。河井さんがプロデューサーを務め、前田さんがアソシエイト・プロデューサーとして参加した岩井俊二監督96年の作品『スワロウテイル』を振り返るところから、カンファレンスがスタートしました。
無国籍感が漂う架空の都市“イェン・タウン”の構築にアジア数ヵ国をロケハンしつつも、「岩井監督の『香港はどう切り取っても香港なんだよね……』ということで、種田さんに作ってもらうしかないということに。クランクインの1ヵ月前ですよ(笑)」という前田さん。「とにかく時間がなかったですね。デザインを考えてから作っていたわけじゃないですし。夢中でやっていただけなんですね」(種田さん)、「監督とプロデューサー、美術監督との打ち合わせもなかったです。みんなが同じ方向を向いて走っていた作品ですね」(河井さん)。「一番のピークはアヘン窟のシーン。美術部が当時多発的に作っていて、誰も作業をやめないんです。それでふと気がついたら後ろにカメラがあって、岩井監督が『ねえ、もう撮ってもいいかなあ……?』って(笑)」と当時の熱気を語った種田さんは、岩井監督と組んで数々の傑作を生み出してきた名カメラマン、故・篠田昇さんにも触れ、「当時40代で一番ノッているころで、篠田さんがムードメーカーとして全員を引っ張っていってくれました。『スワロウテイル』以降は、撮影も美術も本当に似たようなものが増えたんですね。篠田さんが大きな功績を残したことはちゃんと伝えておきたいです」と述べました。

©2010 TIFF
次に登場したゲストは、98年作品『不夜城』のリー・チーガイ監督。「日本映画が大好きなので、日本でやれるならどんな条件でもやりたいと飛びついたんです」とリー監督。種田さんも「ただの日本映画になるわけがないのは分かっていましたから、ぜひやりたいと思いました」と参加の経緯を語りました。
『不夜城』で圧巻なのは、冒頭で金城武さん演じる主人公が新宿・歌舞伎町の喧噪を通り抜けて、路地奥にある自室へと入っていく5分間にわたる長回しのシーン。歌舞伎町のロケと、その場に組んだオープンセットの組み合わせで撮影されたこのシーンは、リー監督にとっても「特別なシーン」とのことで、「外の通りから部屋に入って、また通りに戻っている複雑なシーンで、あれは種田さんの素晴らしい美術がなければ成立しなかった」と述べました。また劇中で登場する温泉のシーンは、監督が以前から気に入っていた日本の温泉だったことを告白。「私は“温泉モンスター”なんです。絶対この温泉で映画を撮ってやろうと思っていました(笑)」と明かしました。種田さんは、「(自分の美術について)ディテールがこだわっていると言われることが多いですが、その点については『不夜城』が一番。このディテールのすごさは、その後の作品では無いです」と語り、リー監督は「香港のスタッフだと、私の理想に対して70点どまり。それが種田さんの場合だと200点ものが出来上がってきます。使い切れません」と種田さんを絶賛しました。

©2010 TIFF
『シルク』からは、スー・チャオピン監督が登場。幽霊という伝統的な存在に科学的なアプローチで迫る異色ホラーである同作は、監督をはじめとした台湾のスタッフ、香港の撮影班、日本の美術スタッフと俳優陣、そしてオーストラリアの特殊メイク陣と、国際色豊かなもの。「美術スタッフ4人で台湾に乗り込んでいって、途中からペイント担当3人を呼んだんですが、台湾の色々な美術部が見学に来ましたね」と振り返った種田さんは、スクリーンに映るシーンを見ながら、「何層も色を重ねて油絵のような色調を意図的に作りました」など、技術面を解説しました。
同作に主演し、マッドサイエンティストに扮した江口洋介さんからは、「常に台本でイメージしている以上のセットが組まれているんです。イマジネーションの限界に挑む人だと思います」とビデオレターでメッセージが。スー監督からも「種田さんは天才です」と賛辞が送られ、「この映画のあとは台湾でも同じようなセットが増えました。単に一緒に作品を作ったというだけではなく、仕事の進め方も含めて、台湾の映画界に大きな影響を与えた方だと思います」と称えました。

©2010 TIFF
そして最後のゲストとして登場したのは、99年の『死国』で映画デビュー、『キル・ビルVol.1』にも強烈な印象を残す“ゴーゴー夕張”役で出演した栗山千明さん。栗山さんは、セットが持つ力について「(演技に対する影響が)すごく大きいです。私の場合は、粗を感じてしまうとそれが気になってしまうんですが、(完成度が高く、意図が)ハッキリしていると、気持ちから演技に入っていけるんです」と語り、「『キル・ビルVol.1』の青葉屋(クライマックスでユマ・サーマンが大立ち回りを繰り広げる日本料亭)のセットを私が次々に壊していくんですが、あまりにも見事でもったいなくて躊躇していると、種田さんが『映画のセットは壊してはじめて成立するんだよ』と言ってくださって、ぞぞぞっとしました」と感動したエピソードを披露しました。
『キル・ビルVol.1』については、先の前田さんとのトークでも、「種田さんを引き合わせた際に監督は一発で気に入ったみたいで、“映画好きの少年”という自分と共通するものを感じたんだと思います」というタランティーノが種田さんを起用した理由のほか、「意図は明確だけど、言うことがコロコロ変わるんです。ハプニングが毎日で、その度にタランティーノが『タネダさんを呼んでくれ』って」(種田さん)という理不尽な要求に次々と応えていく種田さんの仕事ぶりに、「このスタッフは本当に感動モノでしたよ」と前田さんが感動したエピソードなどが語られていました。
「いつも変わらず接してくださるので安心できます。次の現場が種田さんだと分かるとすごく楽しみにもなりますし、台本で想像していたものが目の前にあることは本当に感動します」と種田さんを評した栗山さんに、「僕の中では栗山さんはゴーゴー(夕張)なんですね。“ゴーゴーは生きている”というか。タランティーノをはじめ、みんな大好きですからね」と返した種田さん(栗山さんは「(あのイメージで見られて)怖がられちゃうんですよ……」と苦笑い)、「またぜひ一緒に仕事しましょう」と笑顔を見せました。

©2010 TIFF
台湾での作品を作り終え、いまは中国での撮影に臨んでいるという種田さんは、「今日来てくださったアジアの監督たちと一緒に、もっとアジア映画を作っていきたいです。特にいまは、アジアの中で距離感があるじゃないですか、映画を作ることでそれを越えていきたいです」と心情を吐露。深夜にも関わらず詰めかけた観客からの拍手に包まれて、カンファレンスを締めくくりました。