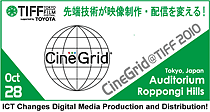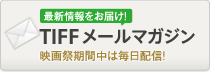2010.10.27
[インタビュー]
natural TIFF supported by TOYOTA 『闇と光の門』アリステア・バンクス・グリフィン監督インタビュー(10/27)


©2010 TIFF
――作りたい映画の見本となるような作品はありますか?
ポール・シュレイダーが提唱する“先験的映画(transcendental cinema)”のエッセンスを取り入れたいと思いました。それとロベール・ブレッソンやタルコフスキーはよく観ていて、私が思うアメリカ映画とヨーロッパ映画の間のような作品を作りたいと思いました。ポール・シュレイダーはそのふたつのスタイルの間を行く指針のような本を書いています。そこに書かれていることと、ブレッソンが映画の文脈の中で演出するということについて書いたものを参照しました。ですが、俳優たちは初期段階から深く関わっています。ブラディ・コーベットは特にそうです。最小限の会話しかない映画にしようと話していましたが、脚本は非常に詳細に書かれています。かなり多くの会話や独白があり、あとで取り除いたのです。
――脚本にはカメラの位置だけが書かれているのだと思いました。
音も含めてあらゆる詳細が脚本に書かれています。登場人物たちの関わりについてもです。撮影するしないに関わらず、俳優たちに知っておいてほしかったのです。プロセスのために理解してほしかった。私はウィリアム・フォークナーの内省的な独白の書き方が好きです。この手の映画のプロセスは、テレンス・マリックがナレーションや序曲を使って表現するものと似ているかもしれませんが、私はもっと最小限で、サイレント映画に近いものにしたかったのです。状況説明や物語にはあまり興味がありません。直感的な反応を引き出せたらいいなと。ですので写実的な作品ではありません。
――設定はどこから着想を得たのですか?
私の子供時代からです。私はあの地域から遠くない街に住んでいました。家族そろって週末になるとその場所に出かけたものです。私が10歳のとき、この小さな土地を見つけて小屋を建てました。それから私は森の奥深くに住む子供たちと交流し始めたのです。彼らは完全に外の世界とは隔絶されていて、おそらく唯一知る街の人間が私だったと思います。
――どこですか?
ミシシッピの南部です。ハリケーン・カトリーナによって最も甚大な被害を受けました。ニューオリンズやメキシコ湾岸地域よりもひどく、たくさんの人が亡くなりました。
――その場所で撮影したのですか?
そうです。カトリーナの前に脚本を書き始めていたので、ハリケーンが来てうろたえました。もともと思い描いていた風景は緑が生い茂っていて、もっと浮世離れした感じの場所でした。カトリーナの後は不毛の土地のようでした。当時はずいぶん落ち込みましたが、その場所でないといけないと分かっていました。私がつながりを感じ、把握しきっている場所でしたから。
――その変化は作品にはどういう影響をもたらしましたか?
600年以上ずっと眠っていた下生えの植物が全部持ち上げられ、風景は一変しました。脚本も変えました。変化と命のつながりについての物語です。ある意味、希望のある作品にしたかったんです。
――しかしトーンは不吉な感じですね。登場人物たちは自然の脅威に圧倒されているようです。
ブレッソンの考えを用いているからでしょう。彼は伝統的な俳優よりもモデルとしての俳優を好みました。
――つまり物語を伝える係ではなく、空間を占める身体としてということですか?
ブレッソンの人物たちは普通でない、あるいは写実的でない風景やフレームを移動しました。彼がしようとしたこと―そして私たちがしたこと―は俳優に最小限の動きをせよということでした。身振りもなし、顔の表情もなし。俳優の頭のなかで起きていることを示す表現は一切させませんでした。そうすることで、すべてが均質化する。それは映像的に平板だということではなく、人間は木と同じく重要だという意味において均質になるということです。
――唯一説明的な会話として、医者が兄弟を訪れる場面があります。
あそこはこの映画をどこかに着地させる必要があった場面で、単に時系列でみて重要な場面というわけではありません。あの場面で、兄弟の行動や行き先を説明する何かを観客に提示するのが適切だと感じたのです。
――俳優たちの言葉には特徴的な訛りがありませんが、それも意図したことですか?
そうです。私にとってあの場所で撮影することは重要でしたが、観客がそれがどこか分かることは重要ではありません。観客には居場所が分からない感じを与えたかったので、現在の話なのか20年前なのか分かるような視覚情報は出していません。美術担当と私で20世紀末なのか、現在なのか限定できないような小道具や衣装を集めました。
――母親の容体や、息子たちに対する彼女の感情も見えにくいですね。
同じ理由からです。すべての要素を意図的に切り離したかったのです。母親には背景の物語があり、息子たちにもある。それは深い部分では脈々と流れていますが、表に出すことには興味がありませんでした。提示のスタイルを変えたかったのです。物語るというより、洞窟の壁画的な方法といえるかもしれません。
――川を下る最後の旅は典型的ですね。どこから着想を得たのですか?
私自身が川下りを何度もしていたので、そこから考えつきました。川は古典文学では重要な役割を担っていますし、私もほんの少しそういう思考を映画に持ち込みたいと思いました。川の細い部分を下るふたりの兄弟のロングショットがあり、川が開けてどんどん広がっていく。移動する彼らを川は飲み込もうとする。風景と一体化していき、ひとりが棺とともに残される。
――この作品がnatural TIFF部門に選ばれたことについてはどう思いますか?
とてもうれしいですよ。私の作品と、もうひとつ『四つのいのち』はカンヌでも同じ部門に選ばれました。両作品とも最低限の会話しかなく、役者には重きを置いていない。今年の映画の特徴だと思います。カンヌで最高賞を取った『ブンミおじさんの森』もそうです。今年のテレンス・マリックの “Tree of Life”もそうですよね。自然のうねりを感じる映画が期待されているのだと思います。

©2010 TIFF
――自然についてはふたつの考え方がある。人類は本来自然の一部であるというものと、反目するものだという考え方。
私はその間に余地があると思います。そのことはブラディにも話しました。彼が演じた男は、自分は世界と協調しあっていると信じていましたから。でも、その男の態度にはどこか偽善的な部分がある。
――鹿の内臓を取り出すシーンでは、彼は気分が悪くなりそうでしたね。
実際になりました。あれは直感的な反応です。彼は未経験者だったので、監修者をつけました。あの鹿は近所の農場で死に運ばれてきたのですが、私たちにはその一度しかチャンスがなかった。農場の人たちは―もう何百回も内臓を取り出しているのに―毎回吐くそうです。ですから自然への尊敬の念を示すため、カットせずにすべて入れ込みました。彼が鹿を屠殺する過程を観たあと、次のシーンでそれを食べているところを観る。連環しているのです。冒頭で彼は鹿を引きずって森を抜けていき、最後に棺を引きずって川岸を上がります。そういう点で、この作品はnatural TIFFの考えを包含しているのだと思います。私は一連の出来事の間にある意味の網を構築したかったんです。そうやって世界は機能しているのだし、自然を離れて都会の環境にいる人や物事にも関連していることなのです。
――母を埋める場所もずっと考えていた場所なのですか?
実はあれは存在しない場所なんです。特殊効果を使いました。木のミニチュアなんです。もしかして言うべきじゃなかったかな(笑)。
――ナチュラルじゃないですね。
本物の木から作ったミニチュアだという点ではナチュラルですよ。でも1メートルくらいしかなくて。この映画では風景を描くために、実はかなり特殊効果を使っています。どういう画がいいかは頭の中にきっちり思い描けているので、それを特殊効果を足して完成させたという感じです。
(聞き手:フィリップ・ブレイザー)
『闇と光の門』
→作品詳細