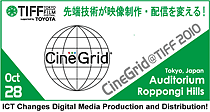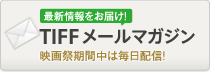2010.10.29
[イベントレポート]
コンペティション 『僕の心の奥の文法』公式記者会見のご報告

Q&A: 10月29日(金) 19:30~ TOHOシネマズ SC7
■ 登壇者 ニル・ベルグマン(監督/脚本)、オルリ・ジルベルシャッツ(女優)


©2010 TIFF
2008年の東京国際映画祭以来、2年ぶりに東京を訪れたベルグマン監督とオルリ・ジルベルシャッツさんに、作品についてのお話を伺いました。
監督: 2度目の参加を光栄に思います。TIFFがますます盛大になったという印象を受けています。
オルリ・ジルベルシャッツさん: ご招待いただいてありがとうございます。世界の素晴らしい作品とともに上映していただけることを嬉しく思います。
Q: 原作は、イスラエルでは有名な小説家による作品ですが、どのようなことでこれを映画化しようと考えられたのですか?
監督: 21歳か22歳の頃に原作を読みました。大きく、そして深く影響を受けました。感情を揺さぶられ、ある意味でショックを受けました。実際は、作家のデイヴィッド・グロスマンより15歳年下なのですが、まるで自分の話を読んでいるような、そんな印象を受けました。ずっと心に残り、私の、そして私の人生の一部となりました。映画の道を歩み始め、長編デビュー作『ブロークン・ウィング』で、エルサレムの国際映画祭に参加した時、その会場の外の階段のところで、グロスマンさんを見かけました。「グロスマンさん、あなたの小説を長編映画にするのが私の夢なんです」と話しかけました。彼はニコリとして、そして少し疑わしい表情で「頑張ってください」とおっしゃったんです。彼が疑念を持ったというのは、この小説が子どもの内面について書かれていて、映画にしづらい素材であるからです。これまで試みた人たちが何人もいるらしいですが、どれも映画として完成されていません。私は3年かけてこの映画を作りました。脚本に多くの時間を費やしました。よく「映画にするなら悪い本を選べと」言います。それは原作を超えられる可能性が大きいからです。逆に傑作といわれている小説を映画化し、成功することは容易な仕事ではありません。でも原作の登場人物があまりにも好きだったので、グロスマンさんの書いたことを70%でも表現できれば、それでも素晴らしい作品であると評価していただけると確信して制作に挑みました。グロスマンさんにも映画は見て頂いています。実は、脚本にもご協力いただいます。ドラフトができると彼に送って、フィードバックをいただきました。好きなようにつくってくれとは言われたものの、例えば60年代当時の話し方など、そういった小さな修正点を指摘してくださいました。大変感謝しています。ラフカットを見ていただいている間、私は自宅でビクビクしながら、彼からの電話を待ちました。電話が鳴って、「とても感情的な体験をして、見終わって30分間誰とも話をせずに余韻に浸っていたよ」と言ってくれたんです。誰からの何よりも嬉しいj評価でした。
Q: 主役の男の子はどうやって見つけたのですか?
監督: 国中を探しました。通常テレビシリーズなどでの子役は、キャスティング会社に協力してもらいます。でもそういった方法では、求めているような男の子は見つけることができないと思いました。そこで、「『僕の心の奥の文法』という作品に主演してくれる男の子を探しています」という紙を持って、イスラエル中の学校を訪問しました。何千人もの男の子たちのオーディションをしました。初めてロイ・エルスベルグに会ったのは、キャスティングマネージャーが彼をオーディションをしている時でした。私がちょっと気になって、彼に「初めて自転車に乗れた時のことを話してくれる?」と言いました。当時、実の息子に補助輪無しで自転車に乗るための練習を手伝っていたので、その質問を思いつきました。「お父さんが練習を手伝ってくれて、転んで痛かったんだけど、お父さんには『全然痛くないよ、大丈夫』って言ったんだ」と感情を込めてその時の出来事を話してくれました。まさに私たちが求めていた、何か目の奥に深い感情が見える、将来、音楽家や映画監督になるような、とにかくアーティスト的な素質を持っている男の子でした。撮影が始まりますと、ますます子供時代のグロスマンさんに似ているということに気づきました。
Q: その主演のロイ君について、母親役を演じられたオルリ・ジルベルシャッツさんとしてはいかがでしたか?
ジルベルシャッツさん: 彼はプリンスだわ!それがまるでいつもの自分の様に演技も自然でした。ほとんどの俳優は、ストーリーのシチュエーションを理解し、その役どころになりきれるよう、ものすごく努力するわけでだけど、彼には生まれ持った素質があるのね。」
Q: ご自身は、どのようなことに気を付けながら演技されたのですか?
ジルベルシャッツさん: 私が演じた母親は、本質的に意地悪で、残酷で、脅迫的です。撮影中も、子どもに対してもう少し寛大で情け深くあってほしいと願ってしまったくらいです。でもグロスマンさんが描いた母親を演じられるように努力しました。彼女は女性としても辛い人生を歩いて来たことから、自分の息子の感受性を受け止めてあげることができなかったわけです。私には3人の子どもいましたので、この冷酷な母親を演じるのは、とても難しいことでした。
また、同日に開催されたQ&Aセッションでは、エンディングの余韻の残る中、日本ではあまり馴染みのないユダヤ文化についてもご説明いただきました。ユダヤ教徒の子供は、男児が13歳、女児が12歳になると『バト・ミツワー』、つまり、ユダヤ法を守る宗教的・社会的な責任を持った成人と呼ばれるようになります。映画の中に子供がこの責任を持てる年齢に達したことを記念して行われるユダヤ教徒の成人式のシーンが出てきます。今では、人によってはそれほど宗教色の濃い儀式ではありません。つい最近、女優のオルリ・ジルベルシャッツさんのお嬢さんがバト・ミツワーを迎えたということで、「そのお祝いとしてこの東京国際映画祭に娘を連れてきているのよ」と会場にいたお嬢さんを紹介し、会場から温かい拍手が贈られました。
それから火の周りを囲んだ儀式のシーンについては、「これは1960年代に始まったものです。その頃のイスラエルはまだ若い国で、第二次世界大戦あるいはホロコーストの犠牲者が集まって来ていました。そして、子どもたちがホロコーストのような悲劇に遭わないように、強い人間に育てようという団結心から始まりました。映画の中では、ちょっと変わった子どもであるアハロンが一度飛び込むべき輪の中に二度も飛び込んでしまいます。」
『僕の心の奥の文法』

©Libretto Films - Norma Productions