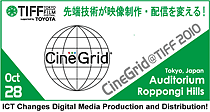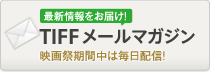2010.10.30
[インタビュー]
コンペティション 『ビューティフル・ボーイ』 ショーン・クー監督 インタビュー(10/30)


©2010 TIFF
――銃乱射事件にどのような衝撃を受け、どんなことを考えながらこの映画を作ったのでしょうか?
実はバージニア工科大学というのは私の両親が卒業した大学であり、妹が生まれた場所でもあったので、個人的にショックを受けました。犯人がアジア系だったこともショックでした。それが最初のインスピレーションになりました。もうひとつは、仲のよい友だちが私の家で亡くなり、彼の家族の悲嘆を目の当たりにしたことです。この映画に表れる悲嘆の部分は、この家族の体験にインスパイアされたもので、私は映画をこの友人に捧げています。
また、もし私が無差別殺人のような事件を起こしたら、両親はどのように反応するだろうかということも考え、このようなかたちになりました。映画に登場する両親には、私自身の両親がベースになっているところもあります。
――実際の事件では犯人はアジア系ですが映画では白人です。どのような意図で変更を加えたのでしょうか?
ひとつには、訴えられないように、自分たちを守るためということもあります。それと悲しいことにアメリカで映画を作って、主人公がすべての人々を代表しているのだと観客に感じてもらうためには、白人にする必要があるんですね。主人公をアジア系や黒人にすると、それぞれの人種のための映画とみなされてしまい、白人にしたときだけ誰にでも当てはまる映画になるのです。でももちろん、いろいろな人種のことを意識していましたので、弟の妻や子供をアジア系にするなどして、白人社会だけで起こる現象ではないことを示唆しています。

©2010 TIFF
――映画では事件に関する説明や情報を削ぎ落とし、両親の視点や世界に限定していることが緊張感を生み出しています。
悲しいことにアメリカではこのような乱射事件が頻繁に起こっていて、テレビでもネットでも情報が溢れています。でも犯人の両親については見えてきません。隠れてしまうことが多いからです。コロンバインもバージニア工科大学の場合もそうです。彼らも自分たちの子供を失ったのに、マスコミからは叩かれて、子供の死を悼む時間さえ与えられていないような感じがします。
私たちの社会は、事件が起こると誰かを責めたがるのですが、犯人が自殺してしまうことが多いので両親が悪者になります。でも、本当はそんなに単純なことではないと思います。自分が17歳とか18歳のときのことを考えても、両親が完全にコントロールしていたわけではない。それなのに簡単な答えを求めてしまう。そういうことをヒントに、両親の立場を想像して描きました。
――なぜ父親役にイギリス人のマイケル・シーンを起用したのでしょう。彼が話す英語はアメリカ人のアクセントになっているように感じましたし、他の出演作と比べると顔がふっくらしているように見えたのですが…。
とてもいい俳優で、ファンだったんですね。小さい映画なので本人がやりたがるだろうという狙いをつけてアプローチする必要がありました。彼は社会的な地位のある実在の人物を演じることが多かったので、普通の父親をやりたがるだろうと考えたのですが、喜んで引き受けてくれました。
彼と最初に会ったときにアクセントの話はしませんでした。自分なりにアメリカ訛りを作ってくるか、あるいはそれがうまくいかなければイギリス人という設定でもかまわないと思っていたのですが、彼はアメリカ英語をきちんと習得して現れました。私も太ったかなと思ったんですが、怖くて「太りましたか?」とは聞けませんでした(笑)。でも役作りの一環としてやる人だと思いますし、ちょっと太ったことでより役にあうようになったと思います。
彼は衣装合わせでも、ぴったりではなく、ちょっとダボッとした感じにしてほしいと言っていました。自分がよく見えるのではなく、役柄がより自然に見えることをとても大切にしている。だから私は、わざと太ったのではないかと想像しています。
――この両親が暮らすサバービアは安全で幸福に見えますが、実はそれは物質的に豊かなだけであって、家族の絆は形骸化し、希薄になっている。そういう視点も盛り込まれていると思ったのですが…。
そのとおりです。あの家のなかにはたくさん写真が飾ってあります。以前は本当に幸せだったのかもしれませんが、いまは昔の写真を家中に飾ることでまだ幸せなのだと思い込もうとしているわけです。素晴らしい家やいい仕事など、外側からは完璧な家族に見えますが、寝室は別々ですよね。この夫婦は外見をつくろっていますが、関係は壊れている。そういうことも意識して表現しました。
――この映画は、銃乱射事件とは別に、そういう生活を送る家族が一度すべてを失って純粋な個人に立ち返り、お互いを確認しあうという普遍的な物語になっているように思えます。
そういうふうに見ていただいてとても嬉しいです。というのも観客のみなさんには、キャラクターのなかに自分を見たり、感じたりしてほしかったからです。たいてい夫か妻のどちらか一方に共感して、両方に共感する人があまりいないんです。映画を観て、家に帰って子供を抱きしめたというのが、私にとって最大の褒め言葉です。願わくはこの映画を観て、人との関わり方がちょっとでも変わってくれたらと思います。
アメリカに打撃を与えたサブプライムローンやリーマン・ショックは、もとをたどれば家を持つというアメリカン・ドリームと結びついている。家を持つのは決して悪いことではないが、それだけが夢や幸福ではない。この映画はそんなことも考えさせる。アメリカからまたひとり、豊かな才能を持つ監督が登場してきた。
(聞き手:大場正明)
『ビューティフル・ボーイ』
→作品詳細