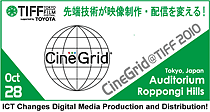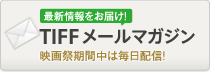2010.10.28
[インタビュー]
アジアの風『追伸』ヤルキン・トゥイチエフ監督インタビュー(10/28)


©2010 TIFF
――この映画の製作会社であるウズベクフィルムは国営撮影所で、ワールドセールスを行っているウズベクキノも国営の映画会社ですよね。国が映画振興に非常に力を入れているということですが…。
確かに、中央アジア各国の中で、ウズベキスタンだけが唯一、映画産業に国家が補助金を出しています。年間に35mmフィルムで15本、ビデオが60時間、12~15本のアニメが製作される計画で、それら全てに国家から資金が提供されます。
――国全体が映画好きなんでしょうか?
ウズベキスタン映画の振興に関しては、まず大統領令があります。映画産業のレベルアップを目標としています。もちろん映画は国民に愛好されてもいます。さきほどお話した国家の資金で作るもののほか、民間ベースで製作されるものも、ビデオになりますが年間で45本くらいあります。

©2010 TIFF
――みなさんはどんな映画を好んで観るんでしょうか。
私の見たところ、日本人も日本映画がお好きですよね。同じように、ウズベキスタン映画が好まれます。外国映画は、アメリカ映画のブロックバスター映画、あとはロシア映画がよくかかりますね。
――都会で教職についている弟と田舎で母親と暮らしている兄の対比が全編を通して強調されています。これは、実際にウズベキスタンにある問題を反映したものでしょうか?
私がこの映画で示したかったのは、実際のウズベキスタンではなく、生活に目を向けないでいると、そのうちに悪意が表面に現れてくるということです。ミノタウロスの話がでてきますが、弟が語っている様々な言葉は、ただの言葉に過ぎない。しかし兄の方はその言葉をエモーショナルに、自分の体験として受け止めてしまう。そして彼らの間に葛藤が生じます。弟にとっては、言葉は空虚なものと化しているのですが、兄にとってはリアルなものとなってしまうのです。
私は人類共通の問題を示したかった。世界中で、過去に蓄積されてきたものが、力を失っているように思うのです。例えば日本人ももう着物を着て歩くわけではないですよね。
――ハミッドが雷に打たれてから、様々なものが違って見え始める。そのことが鏡を見ること、タイルが崩れること、糸を張り巡らせるシーンなどに反映されています。モスクワで脚本を勉強されたそうですが、脚本はとても精密なものなのではないかと思いました。撮影しながら脚本を変更した点はありますか?
私は脚本家であり、映画監督です。脚本家としてはきちんと最終バージョンを仕上げるのが仕事であり、監督としてはやはりアイディアにそぐわないものは取り除けたり変えたりします。ラストシーンが一番難しかったです。ワンカットで撮るのが難しく、現場で刈り取り機を発見して、それを使うことでやっと撮れました。
――タイトル『追伸』にはどんな意味が込められているんでしょうか?
私が言いたかったのは、人がこのように生きたらどうなるか、大きな危険が待ち受けているだろうということです。今度は本当に恐ろしいことが起きてしまうかもしれない。人生の様々な出来事にはみなそれぞれの追伸があると思います。現代社会は精神性が失われてきている、精神性が単なる付け足しになってしまっている。かつては手紙を書き、一週間かかって相手に届いた。書き手のエネルギーがそこにあったけれど、今はSNSでやりとりする時代です。かつては奇跡であったものが、ありふれたものになってしまっている。
――次回作の予定を教えてください。
次回作の予定はまだないのですが、ウズベクフィルムで私の脚本による『遅い人生』『9ヵ月』という2本の作品が編集中です。
(聞き手:夏目深雪)
追伸
→作品詳細