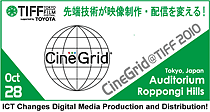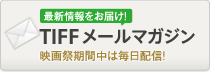2010.11.05
[インタビュー]
コンペティション審査委員長 ニール・ジョーダン監督 インタビュー

©2010 TIFF
――初めて国際映画祭の審査委員長を務めての感想は?
私は、自分の映画を映画祭のサーキットに乗せようと考えたことがありません。これまでハリウッドの大作もつくっているし、本当に低予算の映画もつくっているが、映画祭から映画祭へ渡り歩いてきた監督ではないのです。今回は依頼を受け、国際映画祭がどういうものであるかもっと知りたいという気持ちになりました。特に東京は素晴らしい街ですし、『狼の血族』で参加して以来、東京には来ていますが、映画祭には来ていませんでしたから。でも、ハードワークで疲れました。
――15本のコンペ作品は、どのような基準で見られましたか?
新藤兼人さんのように98歳で、これまでに多くの作品を撮っている方の作品から、イタリアの監督(マッテオ・ボトルーニョ、ダニエレ・コルッチーニ)のように若い人の初めての長篇監督作もある。非常にバラエティに富んでいて、映画作家のいろいろな視野を見せていただけました。

©2010 TIFF
――映画祭期間中、他の4人審査委員と情報交換はするのでしょうか?
昼食と夕食がほとんど一緒ですから、映画を見た後に食事のおいしさを判断しているのか、映画を判断しているのか分からなくなるくらいです(笑)。特に1日に3本か4本見たときには、必ず1回はそれぞれの意見を交換しておかないと、ごちゃ混ぜになってしまうので。
――賞の選考は、順当に決まったのでしょうか?
皆がこれは、という際立った映画が4、5本ありました。その中から、例えば役者さんたちがとてもうまいとか、監督が見せようとしていることがよく分かるという感じで、いろいろと議論をしなくてはいけないという作品が3本残りました。自分は映画をつくる人間で、今回の審査員の中にも監督が2人(根岸吉太郎、ホ・ジノ)いましたが、審査をしていて、自分たちが審査される側に立った場合、『ここまでは良かったのに、なんでこの後が弱くなるんだよ』などと評価されるのだろうなあという感じでしたね。
――東京サクラグランプリに『僕の心の奥の文法』を選んだ決め手は?
ニル・ベルグマン監督の作品は見たことがなかったけれど、自然な資質とでもいうべきものがとても魅力的だったと思います。『僕の心の奥の文法』は、強いインパクトのある物語で、ラストの3分の1あたりで少しぐらつきのようなものがあったので監督が己を見失ってしまうのかなと心配もしましたが、結末は非常にいい終わり方でした。最終的に残った数本の中にはもっと感情的なものや、観客の受けがいい映画もあったとは思います。でも、自分自身の基準としては、本当に描きたいものをちゃんと描き、もっとも訴えかけてきた作品を選びました。

©2010 TIFF
――16歳のときに新藤監督の作品を見て、影響を受けたそうですが。
ダブリンの映画館で『鬼婆』と『本能』を見て、とても影響を受けました。リメークしたいと思ったくらいです。
――では、新藤監督の『一枚のハガキ』に審査員特別賞を贈れたことは大きな喜びだったのでは?
審査委員として見なくてはいけなかったので、期待にかなう映画であるかどうか心配でした。でも、とても美しい、いい映画でした。短かったですが(授賞式の)ステージで話す機会があり本当にうれしかったです。
――審査委員長という大役をまっとうされたことで今後、ご自身の映画づくりに影響はありますか?
自分の作品に関して、もっと厳しく批判的になるでしょうね。とてもいい経験をさせてもらいました。今後、脚本を書くときには、今回の4人の審査委員がどういう気持ちで読むか、そういうことを考えながら書くのかなと思っています。
――現在、新作の編集中と聞きました。完成したら、ぜひ来年の東京国際映画祭で上映してください。
I HOPE SO!(そうなるといいですね)

©2010 TIFF
疲れとともに、重責を果たした安堵もあったのだろう。ジョーダン監督の柔和な表情からは達成感がにじみ出ていた。
(聞き手:鈴木元)