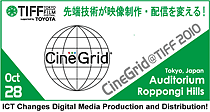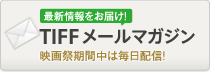2010.10.28
[インタビュー]
コンペティション『鋼のピアノ』 チャン・メン監督、ワン・チエンユエンさん(俳優) インタビュー(10/28)


©2010 TIFF
――『鋼のピアノ』は1990年代前半の中国東北部の街が舞台と解釈してよいでしょうか。
メン監督(以下 メン): 具体的に何年のどの街と特定してはいませんが、国内の改革開放政策が進んで東北部の重工業地帯が打撃を受けた時代が舞台なのは確かです。1980年代半ばから90年代末までの世情を背景にした物語です。
――その時代を題材に選んだ意図をお聞かせください。改革開放が本格的に進んだのは鄧小平の「南巡講話」が発表された1992年からだと思いますが。
メン: 1992年、僕はまさに東北部で暮らす17歳でした。青春真っ只中の時期の記憶はとても鮮烈です。同級生の家族は、仕事をするにせよ結婚するにせよ、誰もが大きな変化の波を受けて生きていました。現在の東北部は経済的安定を取り戻していますが、当時は非常に微妙な時期でした。そんな時代を生きた労働者階級がいたことを映画にしたかったんです。

©2010 TIFF
ワン・チエンユエン(以下 チエンユエン): 僕も監督と同じ東北部出身で、当時はまだ精神的に幼い人間でしたが、あの時代の空気は考え方に大きな影響を与えています。社会の変化をまともに受け止めたのは僕や監督よりもう一つ上の世代、父や父の友人、おじさんにあたる年齢の人たちでしょう。しかし、その尻尾の辺りに自分たちも存在していたわけで、その時代にとても興味を掻き立てられるんです。

©2010 TIFF
――実は序盤は、どういう映画か掴みかねました。ところが鉄のピアノ作りが始まると、チェンや仲間たちが実はみんな熟練工だったと分かる。いかにもしょぼくれたように見えた男たちが、後半に進むにつれて輝き始める。
メン: あの世代の人たちは中国では〈失われた階級〉と呼ばれています。失業して国有工場から追い出された労働者のことです。『鋼のピアノ』の、停滞した状況にいた彼らは後半、閉鎖された工場に戻ります。全て鉄製のピアノを作るという、半ば酔狂な行為を通して彼らはかつての自分の技術を甦らせ、労働の喜びをもう一度見出すわけです。
――こうしてお会いするチエンイエンさんは大変スマートなのに、演じる主人公のチェン・グイリンは仏頂面でワガママで(笑)。しかし、家族思いで仲間思い。少ない表情から人柄がよく分かる見事な演技です。演技プランとキャスティングについて教えてください。
チエンユエン: 人物像は監督の意志に基づき相談しながら作り上げていきました。ただ、あの時代の東北部の大人たちの雰囲気は感覚でよく分かります。まさにああいう、ぶっきらぼうな感じだったんです(笑)。例えば30代でも今とはまるで違い、みんなすごく老成して見えましたよ。ですから、記憶に残る人たちを思い出すように演じました。
メン: チェン・グイリンは、シナリオを書きながらだんだん出来上がっていったキャラクターです。外見は、とにかく背が高くて痩せている男。そして冬にコートを着ていても寒そうに見えるタイプ(笑)。粗暴な態度に見えるのに目が優しくて、こいつはいい奴だと観客にすぐ見抜かれるような。男から見ても女から見ても、どこか哀れで放っておけなくなる……。ここまでイメージが固まったところで、ああ、ワンさんならぴったりじゃないかと頭に浮かんだんです。彼は93年に中央戯劇学院に入学して、僕は同じ学校に95年に入学。先輩後輩の仲です。これも縁だったと思います。
チエンユエン: 2人とも東北部出身で同じ学校で。監督は前からよく知っていて、とても信頼できる存在でした。そうそう、監督のお父さんも監督で、僕の父も俳優(本作にもベテラン技師役で出演)です。共通点が多いんです(笑)。

©2010 TIFF
――監督はデビュー作『Lucky Dog』(07)の後、ドキュメンタリーを手掛けていたとか。その経験は本作の演技指導などに反映されていますか。
メン: ドキュメンタリーを2本撮っていて、その経験はとても大きいですね。ドキュメンタリーでは冷静な目で被写体を追うことが必要になりますから。『鋼のピアノ』の、近過去をリアルに再現する演出に役立ったと思います。ただ、あの時代にあった真実をより記憶通りに描くためには、リアリズムだけでなくシュールな表現も必要だった。(工場の屋内に雪が降るなどのシーンは)現実の中に非現実的描写が同居するマジック・リアリズムの雰囲気を出せるよう意識して撮りました。(*監督の好きな映画は黒澤明作品とイタリアン・ネオリアリスモとのこと)
――チェンの鉄のピアノ作りは、きっかけは娘のためですが、次第に自分の青春に決着をつける行為に変化していると感じました。チェンの再出発を示唆する終盤と、工場のシンボルだった煙突が壊されるシーンは、ひとつの時代の終わりというテーマでつながっていますか。
メン: 社会があまりに早い速度で前に進むなか、チェンと仲間たちは鉄のピアノを作ることで、労働者階級が誇りを持って暮らしていた時代の記憶を残そうとします。ただ、そこに自分たちがもう戻れないことは、彼らにはよく分かっているんです。煙突が倒れるのは、その誇りの記憶が壊れていくことを意味しています。彼らは40年近くいた自分たちの場所を失う。しかし、再度の変化が待っています。
今は、自分たちが歩んできたこれまでの人生を肯定しつつ、また新しい局面に向かい合うことが可能な時代だと思います。人は社会の変化に直面しながらなおそれを受け入れ、適応しつつ生きていく。これがこの映画のテーマだと言えます。
――次なるコンビ作を期待しています。監督の全く別の映画の隅っこにチェン・グイリンが出てきて、しぶとく生きている姿を見せてくれたとしても痛快ですよ(笑)。
チエンユエン: またぜひ監督とは組みたいです。その可能性はありますよ。
メン: 次のシナリオに、チェン・グイリンの出番を書きましょうか(笑)。
(聞き手:若木康輔)
鋼のピアノ