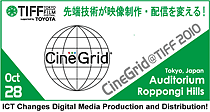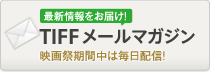2010.10.27
[イベントレポート]
「戦争をやってはいけない。戦争は人間を抹殺します。」 コンペティション 「一枚のハガキ」公式記者会見

■ 登壇者 新藤兼人(監督)、豊川悦司(俳優)、大竹しのぶ(女優)

©2010 TIFF
新藤兼人監督(以下、監督) :今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。
豊川悦司さん: 皆さん、こんにちは。この映画が東京国際映画祭に参加できることを大変嬉しく思います。
大竹しのぶさん: 新藤組でまた一本の映画を完成して、たくさんの人に見てもらえることを嬉しく思います。
Q: 戦争が人間の心に与える傷の大きさと、人間の根源的な生きる力を感じました。映画が完成した今、映画に対する想いを教えてください。
監督: 戦争をやってはいけない。戦争は人間を抹殺しますから、いかなる理由があっても絶対に戦争はやってはいけない、というのがテーマです。一人の兵士が戦地へ行きますと、その後方の家庭が壊されます。奥さんが未亡人になります。それから一家の中心となって働いてきた人が死にますと、一家が砕けてしまいます。そういう戦争の悲惨さをですね、私の経験を通じまして、私は戦争に行きましたので、その体験を通じましてドラマを描きました。
Q: 本作が最後の作品とのことですが、今後も作品をつくられることを考えていらっしゃいますか?
監督: この映画が最後だということは事実です。それは何故かと言いますと、身体が弱りましたし、それから頭も少し弱りました。それで続けていくのは限界だと思って、これが最後の映画だと宣言して作りました。
32歳の時に軍隊に招集され、終戦を迎えるまでについてお話ししてくださいました。まずは100人の掃除部隊に編成され、掃除が済むとクジが引かれ、出撃命令が下ります。100人のうちの94人が戦死し、新藤監督は生き残った6人のうちの一人として終戦を迎えらえました。
監督: 94人の死の魂がずうっと私につきまとって、これをテーマにして生きてきました。独立プロを立てまして、私の思いのままの映画を作ってきたんですが、泣いていては映画は作れないから、雨が降ろうが火が降ろうが顔を上げて映画をつくって参りました。泣いたこともあります。大地に、地上に叩きつけられて、地面を這いずり回るように映画を作ってきた。そうするうちに60年ほどたちまして、それでふと気がつくと98歳になっていました。だからこれが限界かと思いまして、これで映画作りを降りるつもりです。これしかないので、これからも映画の中に生きて行きます。後はわずかだと思いますから、我慢して映画のことを思いながら生きていきたいと思います。どうか皆さん、小さな映画人の小さな映画ですけれど、どうぞよろしくお願いします。
Q: 戦争を生き残った者として今の時代をどう見ていますか?そして、これからを生きるものとして、豊川さんと大竹さんも一言お願いします。
監督: 戦争を止めないと国が育たない、国家が成立しない、だから核兵器を止めようというようなことを言っていますけれど、それはごく当たり前のことです。私が考えているのは、戦争は二等兵がやるんです。今そのことを告げたいんです。偉い人がやるんじゃなくて、二等兵や一等兵がやるんです。それは貧しい家庭をやっと保っているような状況で、戦争に行った兵士が死ねば家庭はむちゃくちゃですね。それが戦争だと、それが戦争の本質だということを、伝えたいです。そういった視点から、核のことを、原爆のことを考えてもらいたい。事実に基づいた私の身の上がありますから、力強く自信をもって発言したいと、この映画をつくりました。

©2010 TIFF
豊川さん: 今の時代ということですが、世界的に見ると1900年前半と2000年代初頭も、実はあまり変わっていないのではないかと。日本では確かに、今は戦後60年といわれ、内戦もなく対外的な戦争もありませんけど、世界的に見れば至る所で内戦があったり民族紛争があったり、または国と国の資本主義的な意味合いでの戦争があったりと、何も変わっていないんじゃないかと思います。監督のおっしゃっている、戦争の中で常に犠牲になるのは一般市民であったり、女性や子どもであったり、父親を亡くしたりあるいは家族全員亡くなってしまったり・・・戦争をすると決めた人たちじゃない人たちが常に戦争の犠牲になっているという現状は、たぶん全然変わっていないと思います。そういう意味においてこの映画が世界の至る所で共感してもらえると考えています。

©2010 TIFF
大竹さん: 監督や豊川さんがおっしゃった通りです。先ほど監督が「小さな映画人の小さな映画」とおっしゃいましたけれど、その映画の中で伝えるために役者の仕事をしています。映画を見た人々の心の中の記憶としてその思いが続いていけばいいなと思います。監督の思いや、私たち映画をつくったスタッフの全員の思いが、映画を通して人々の心にちょっとでもつながっていけばいいなと思いますし、それを信じて作品をつくっていきたいと思います。

©2010 TIFF
『一枚のハガキ』

©2011「一枚のハガキ」近代映画協会/渡辺商事/プランダス